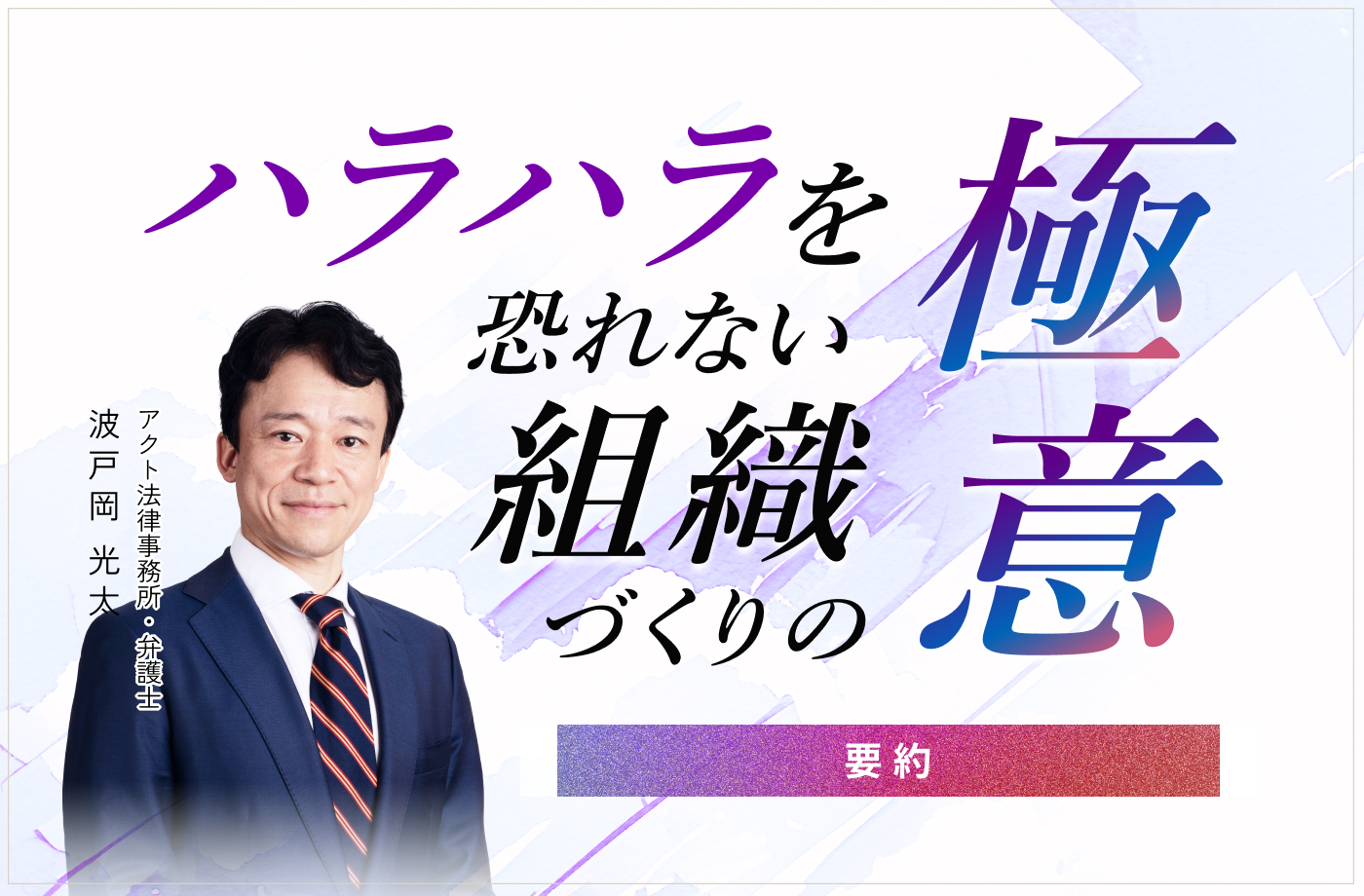
ハラハラを恐れない組織づくりの極意【要約版】
本記事は『ハラハラを恐れない組織づくりの極意』の要約版です。
ハラスメントの種類が多様化する中で、ハラスメントの「強い立場(上司)から弱い立場(部下)」という構図にも変化が出始めています。健全な関係性からより良い組織成長を図るうえでは何が必要なのでしょうか。
本記事ではこの新たな問題提起である「ハラハラ」について、別記事『「良かれと思って」に潜むハラスメントの可能性』でもお話をお伺いした、弁護士 兼 当社パートナーエグゼクティブコーチの波戸岡 光太氏にインタビューを行いました。ハラハラの実態から、組織に与える影響、また具体的解決策までを明らかにします。

Interviewee
波戸岡 光太
ビジネスコーチ株式会社 パートナーエグゼクティブコーチ
アクト法律事務所・弁護士
認定プロフェッショナルエグゼクティブコーチ
企業とビジネスパーソンをもりたてるパートナーとして、法的アドバイス、対外交渉、契約書作成、人事労務問題の予防・解決を中心に取り組む。ビジネスコーチングスキルを兼ね備える数少ない弁護士であり、依頼者と伴走し解決を目指す取り組みは高い評価を得ている。
クライアント会社は不動産、建築、IT、美容、アパレル、機械製造、教育事業などと幅広い分野に及び、これまでの法律相談数は1000件を超える。
近年「ハラスメント・ハラスメント(ハラハラ)」という新たな問題が顕在化しています。これは主にメンバーや下の立場の人からの過剰な反応によって、上司や経営者が萎縮し、組織のコミュニケーションや指揮命令系統が機能不全に陥る現象です。
【主なハラハラのケース】
ケース1:ハラスメントには当たらない、もしくは微妙な事柄への過剰反応
上司や経営者は「腫れ物に触るかのようなコミュニケーション」を強いられ、何も言えなくなり、組織のコミュニケーションや指示系統が機能しなくなる
ケース2:実際に過剰な反応はされていないが、上司が普段から萎縮
上司や経営者が自身の発言に対してハラスメントと指摘されることを恐れるがゆえに、起こすべきアクションにブレーキがかかってしまう(広義のハラハラ弊害)
このハラハラを引き起こす人に、年齢やキャリアによる顕著な差はありません。コミュニケーション不全が原因で次第にハラハラを引き起こすようになる方もいます。
このハラハラが組織に与える影響は大きく3つです。
【影響①:上司や経営者の精神的負担の増加】
上司や経営者は必要以上に気を遣うようになり、最小限の指示のみの関係になる傾向がある
【影響②:組織のコミュニケーション不全と機能低下】
ハラハラをする人との関わりを避けることで情報共有が滞り、組織としての臨機応変な対応や新しい戦略立てが困難になる
【影響③:社員のモチベーション低下と離職の可能性】
仕事の依頼や相談のしづらさから周囲のモチベーションが低下し、離職を検討し始めるメンバーも出てくる
ハラハラが発生する背景には、主に2つの要因があると考えられます 。
要因①:
「自分が組織を動かしている」という認識と、上司や経営層に対する心理的反発によるもの
(上は何もしてくれない、分かってない、という感情的反発)
要因②:
上司や経営者とのコミュニケーション不足によるもの
(仕事の話以外の、組織マネジメント全体に関わる対話不足)
ハラハラを恐れない組織をつくるためには、コミュニケーション機会の創出と法的知識のアップデートが有効です。
- コミュニケーション機会の創出
ハラハラをする人とのコミュニケーションを意識的に行い、期待やビジョンなど組織マネジメント全体の話をしていく。不満の背景をコーチング的関わり方で聴く - 法的知識のアップデート
法的リテラシーを高めるために、会社としてマニュアルやセリフ集を用意、またハラスメント研修を実施する
特に、ハラハラをしてしまう人にはコーチングが非常に効果的であり、ハラハラの根本原因の明確化につながります。
中でもビジネスコーチングは特に有効です。
ビジネスコーチングのポイント
・ビジネスの場面におけるリーダーのあるべき姿やキャリアに関する話からアプローチが可能
・ビジネスパーソンとしてのキャリアがあり、ビジネスに対する深い知見や理解のある人が
コーチとして関与
・ビジネスの現場で起こりうる様々なケースを踏まえた対話が可能
「ハラハラ」は、組織のコミュニケーションや指示系統を機能不全にさせ、上司や経営者の精神的負荷を高めるだけでなく、社員のモチベーション低下や離職の可能性を引き起こす、重要度の高い問題です。健全な関係性からより良い組織成長を図るために、ぜひ前向きに取り組んでみてはいかがでしょうか。
>>ハラハラを恐れない組織づくりの極意【前編】はこちら
>>ハラハラを恐れない組織づくりの極意【後編】はこちら
