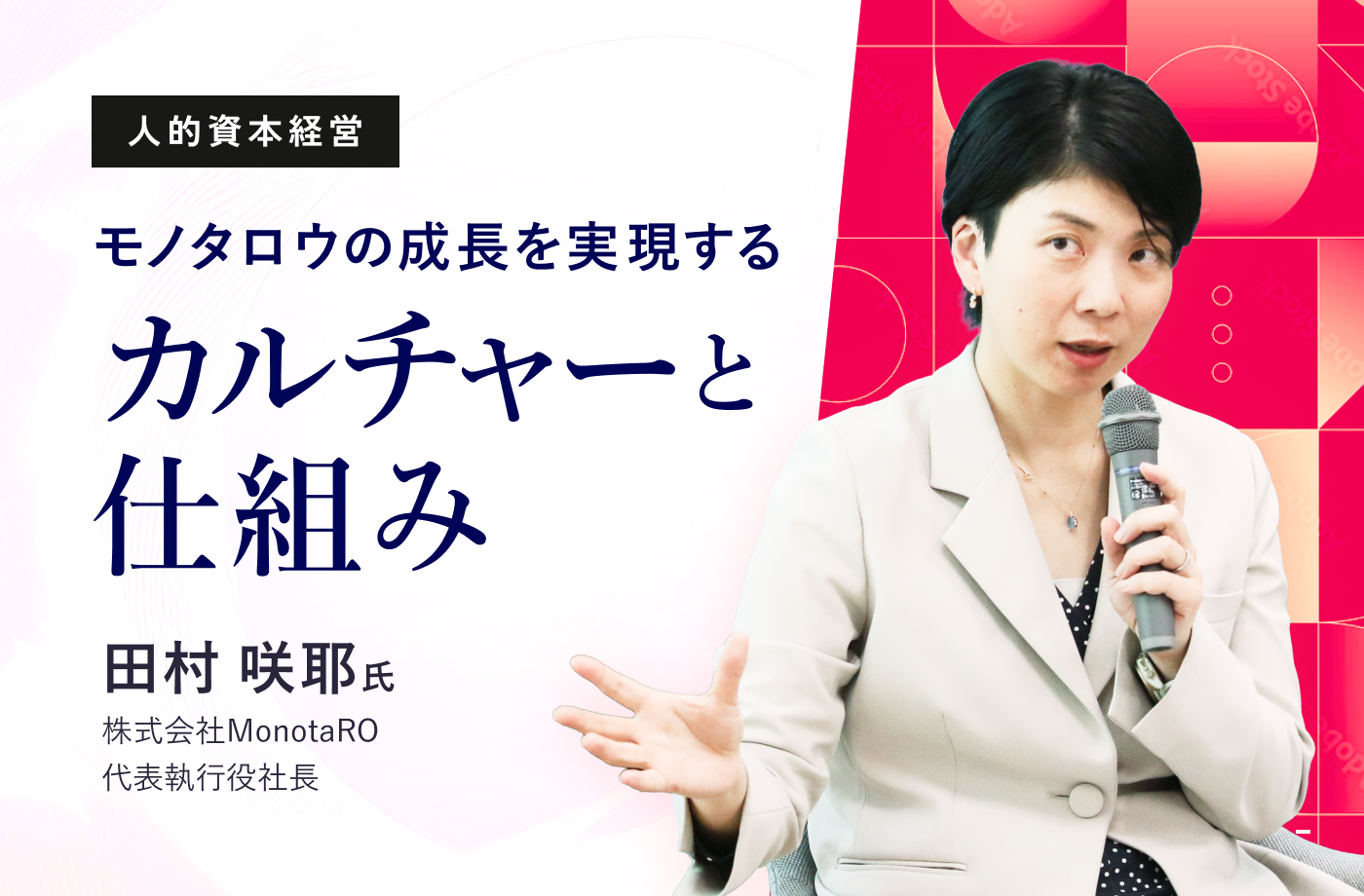
モノタロウの成長を実現するカルチャーと仕組み
INDEX


speaker
田村 咲耶 Tamura Sakuya
株式会社MonotaRO 代表執行役社長
東京大学大学院経済学研究科修士課程修了。ボストン・コンサルティング・グループを経て、GEヘルスケア・ジャパンに入社。マーケティング、工場のデジタル化推進、世界規模のサプライチェーン戦略の構築を担当。2020年3月にモノタロウに参画し、データや最新技術を活かしたサプライチェーンマネジメントの高度化・差別化を統括・推進。2023年6月にはBPM(ビジネスプロセスマネジメント)推進室長に就任し、全社的なプロセス改善とデジタル化の加速を図る。2024年1月には代表執行役社長(現任)に就任し、経営のトップとして事業の持続的成長を牽引している。
1. はじめに
間接資材(MRO)のオンライン通販を手掛ける大手企業であり、驚異的な成長を続ける株式会社MonotaRO(モノタロウ)。同社は「資材調達ネットワークを変革する」というミッションを掲げ、インターネット技術を駆使して従来の流通における非効率性の打破に挑み続けています。その勢いは目覚ましく、中長期的には、単体で毎年15%の継続的な売上成長、および、現在3%の市場シェアを2倍以上に引き上げるという野心的な目標を掲げています。
この急成長を支える根幹には、変化を恐れずに新たな取り組みに挑戦し続ける企業文化があります。そして、その挑戦を可能にするのが、徹底した「人材育成」へのコミットメントです。提供価値の高度化、そして持続的な成長のためには、社員一人ひとりが主体的に考え、行動し、成長していくことが不可欠であると、モノタロウは考えています。
2024年1月にモノタロウの社長に就任された田村氏をお迎えし、同社がどのようにして成長をドライブするカルチャーを醸成し、それを具体的な育成の仕組みへと落とし込んでいるのか、その秘訣に迫りました。特に、創業25年目を迎える同社が、導入10年目となるビジネスコーチングを、次世代リーダー育成や組織力強化にどのように活用しているのか、具体的な取り組みとその効果を詳述します。
2.成長を実現するカルチャーと仕組み
市場シェアを2倍以上への引き上げと年15%成長を目指し、2030年には更なる事業拡大を見据えるモノタロウ。この持続的な成長を実現する上で、独自の企業カルチャーが極めて重要な役割を担っています。それは、社員が共有する6つの行動規範(「他者への敬意」「傾聴」「主体性」「時間資源」「ゴールとプロセス」「モノタロウ魂」)です。
これらの規範の中でも、特に創業以来、核となっているのが「他者への敬意」です。人材確保に苦労した創業期、多様なバックグラウンドを持つ社員が集まる中で、互いの違いを認め、理解し合うことの重要性から生まれた価値観です。この「他者への敬意」が、ミスを恐れず挑戦できる、そして個々の違いを新たな価値創造へと繋げる組織風土の基盤となっています。
しかし、モノタロウはこのカルチャーを精神論に留めません。具体的な「仕組み」によって支えています。
成長を実現するカルチャーと仕組み
■ 会社の継続的な「成長」
成長している環境自体が、失敗を許容し挑戦を促す心理的な安全性を生み出しています。
■ 「データドリブン」な意思決定
「誰が言ったか」ではなく客観的なデータに基づいて判断することで、個人への責任追及を避け、相互尊重と健全な議論を促進します。
■ 気づきと挑戦を促す「人材育成支援」
隔週の1on1ミーティング(以下「1on1」)、週報、コーチング、社内カンファレンス「ManabiCon」といった施策に加え、将来の事業規模拡大や最新技術への挑戦といった機会そのものが、社員の気づきと前向きな挑戦を力強く後押ししています。(育成支援の詳細は後述)。
このようにモノタロウでは、「他者への敬意」というコアバリューを、成長、データ活用、人材育成という具体的な仕組みと一体化させることで、企業全体の持続的な成長をドライブしているのです。
3.社員の「自律的な気づき」を促す、多層的な人材育成の仕組み
モノタロウの持続的な成長は、社員一人ひとりの能力向上なくしては成し得ません。同社では、社員が自ら気づきを得て前向きに挑戦できるよう、OKR、週報、1on1(週次面談)、ビジネスコーチング、社内カンファレンス「ManabiCon」といった多様な仕組みを導入・運用しています。これらの根底にあるのは、「人は他者から言われて変わるのではなく、自ら気づくことで真に成長する」という考え方です。
ここではOKR、週報、1on1、ビジネスコーチングの4つの仕組みをご紹介します。
① OKR:上司の期待値ではなく、客観的な目標達成を追求
目標設定には、Googleなども採用するOKR(Objectives and Key Results)を導入しています。半期に一度、社員自身が目標(Objectives)と測定可能な主要結果(Key Results)を設定し、上司と合意します。この仕組みの大きな特徴は、評価が「上司の期待に応えられたか(Meet Expectation)」といった主観的なものではなく、「設定した目標を達成できたか」という客観的な基準で行われる点です。これにより、上司は評価者というよりも、社員がより高い目標を達成するための「支援者」としての役割に徹することができ、社員の主体的な挑戦を後押しします。
② 週報:全社員による「振り返りの言語化」と経営陣のコミットメント
毎週金曜日、全社員は「その週にやったこと・わかったこと・次にやること・メリット・所感」をまとめた週報を作成し、上司および経営陣に提出します。特筆すべきは、田村社長自らが現在約850通にものぼる全社員の週報に目を通している点です。この「読んでもらえている」という信頼感が、社員一人ひとりの内省を深め、質の高い言語化を促します。「正直大変だが、1200通くらいまでは続ける」と語る経営陣のコミットメントが、組織全体の学びと改善サイクルの高速化に繋がっています。
③ 1on1:メンバー主導の対話による「気づき」と「課題解決」
最低でも隔週で実施される直属上司との1on1は、一般的な進捗確認の場とは一線を画します。これは「メンバーのアジェンダ」を優先し、日々の悩みや相談事を話すための時間であり、上司からの指示ではなく、双方向のコミュニケーションを重視しています。 モノタロウでは、この1on1の「質」にこだわり続けています。2016年、自己流の運用による質のばらつきや不満の声を受け、ビジネスコーチ社によるトレーニングを導入。新任管理職にはコーチング研修を実施し、「ティーチングではなくコーチング」の重要性や、多様なメンバーから話を引き出すスキルを伝えています。また、準備フォーマットの活用や、年2回の「1on1アセスメント」によるモニタリングを通じて、対話が形骸化せず、確実にメンバーの気づきや課題解決に繋がっているかを確認・改善しています。1on1の目的は、単に面談を行うことではなく、「対話を通じて上司・メンバー双方が気づきを得て、前進すること」。特に、自身の考えを上手く言語化できないメンバーから、本音や課題を引き出し、その解決を後押しすることが、組織全体の成長に不可欠だと考えています。
④ ビジネスコーチング:「自ら変わる」を支援する伴走者
約10年前、先代の鈴木社長(現会長)時代から導入されているのが、選抜型の人材開発プログラムであるビジネスコーチングです。対象となるのは、次期部門長・執行役候補といったハイポテンシャル人材や、職位が上がるタイミングで新たな視点や客観的なアドバイスを必要とする人材、そして自ら課題を見つけて変革を起こすことが期待される人材です。 プログラムでは、上司・同僚・部下といったステークホルダーからのフィードバックを参考に、本人が取り組むべきテーマ(例:権限移譲、コミュニケーション改善など)を設定。ビジネスコーチとの対話を通じて、内省を深め、具体的な行動変容へと繋げていきます。田村社長自身も部門長時代にコーチングを受け、その効果を実感した一人です。ここでも重視されるのは「本人の気づき」。外部から言われたことではなく、自らの内側から湧き上がる気づきこそが、持続的な成長の原動力になると確信しています。
これらのOKR、週報、1on1、ビジネスコーチングといった仕組みは、それぞれが独立して機能するだけでなく、相互に連携しながら、社員一人ひとりの自律的な学びと成長を促進し、モノタロウ全体の推進力となっています。
4. 組織の未来を担う、ミドル・経営幹部層への戦略的育成
全社的な育成の仕組みに加え、モノタロウでは組織の中核を担うミドルマネジメント層、特に将来の経営を担う幹部候補の育成に戦略的に取り組んでいます。田村社長自身が「上司に恵まれた」経験を持つこともあり、社員の成長や組織力向上において、部門長や約100名いるグループ長(課長クラス)といったマネジメント層の能力が極めて重要であると認識されています。
中でも、次世代の経営候補と位置づけられる部門長層の強化は、現在の最重要課題の一つです。部門長の人数は2020年の7名から現在は16名へと増加しており、その能力開発は事業の将来を左右します。そのため、モノタロウでは部門長向けのトレーニング機会を増やし、田村社長自らが対話の時間を持つなど、育成への投資を強化しています。
具体的には、月に一度、担当の執行役員が講師となり、以下のようなテーマでトレーニングを実施しています。
ミドル・経営幹部層のトレーニングテーマ
■ 部門運営の高度化
効果的なコミュニケーション戦略、部門戦略の策定、部門長としての役割の再定義、社内外への適切な情報発信の方法などを検討していきます。
■ 全社的視点の獲得
担当部門が持つリソース(人材、予算、ノウハウ等)を、全社戦略とどのように連携させ、相乗効果を生み出していくか、体系的な理解を促します。
これらのトレーニングの中でも、特に重視されているのが「経営構想」の策定と発表です。これは、部門長に一つ上のレイヤーである担当執行役員の視座を持ってもらうことを目的としています。
トレーニングの一環としての「経営構想」策定と発表
課題設定
「もし自分が担当執行役になったら、この部門を今後5年間でどのように進化・高度化させるか?」という問いに対し、目指すべき「ありたい姿」を描きます。そのうえで、現状とのギャップ、存在する課題、そしてそのギャップを埋めるための具体的な戦略やアクションプランを文章にまとめます。
発表とフィードバック
作成した経営構想は、会長を含む全執行役員の前で発表する機会が設けられます。経営トップからの直接的なフィードバックを通じて、構想の解像度を高め、戦略実行に向けたコミットメントを強化します。
このように、モノタロウでは、将来の経営を担う部門長に対して、単なるスキル研修に留まらず、経営者としての視座を高め、戦略的思考力と実行力を養うための実践的な育成プログラムを展開しています。こうした次世代リーダーへの戦略的な投資が、同社の持続的な成長と強固な経営基盤の構築に不可欠な要素となっているのです。

5. 最後に:100年企業へ向けて、進化し続けるための挑戦
これまで見てきたように、モノタロウは独自のカルチャーと多層的な育成の仕組みによって、目覚ましい成長を遂げてきました。しかし、社長就任2年目を迎えた田村氏は、現状に甘んじることなく、さらなる進化に向けた課題認識と強い意志を持っています。
「素晴らしいカルチャーと仕組みがある一方で、日々、この会社をどう良くしていくかを考え続けています」と語る田村氏。今後のモノタロウが向き合うべき、二つの大きなチャレンジについて語ってくれました。
チャレンジ①
企業文化の深化と成長スピードの両立
一つ目は、組織規模の拡大と中長期的に年15%の継続的な成長目標を達成する中で、「企業文化の深化」と「事業スピード」をいかに両立させるかという課題です。社員が増え、かつての「全員の顔が見える」状態から変化する中で、「誰に何を聞けばいいかわからない」「調整コストが増大し、意思決定スピードが鈍化する」といった、いわゆる“組織の成長痛”を感じる場面も出てきていると言います。
「縦割り組織にするのが良いのか、私が週報を読み続けるのが良いのか、正直まだ答えは見つかっていません。しかし、この課題を乗り越え、文化とスピード感を両立できる組織づくりを実現していくことが、今後の大きなチャレンジです」。
チャレンジ②
100年以上にわたり価値提供を続けるための次世代経営リーダー育成
二つ目は、モノタロウが100年以上にわたって社会に価値を提供し続ける企業になるための、「次世代経営リーダーの育成」です。同社には、「資材調達ネットワークを変革し続ける」というミッションを永続的に実現するために、経営陣自身が新陳代謝していくべきだという考え方があります。実際に、約10年周期で社長や役員が交代する仕組みが根付いています。
「この仕組みを維持し、会社が進化し続けるためには、次世代の経営を担う人材を継続的に育成していくことが不可欠です」と田村氏は強調します。現在の経営陣は中途採用者が中心ですが、2020年頃から年間30名以上の新卒採用を本格化させています。一方で、「新卒社員をどう育て、多様でダイナミックな経験を積んでもらうか」という育成体系の構築は、まだ道半ばであり、今後の重要なテーマであると認識されています。
「他社から転職してきたメンバーにとっては素晴らしい会社でも、新卒にとってはモノタロウが全て。この会社の中でいかに成長機会を作っていくか、真剣に取り組む必要があります」と田村氏。
組織規模の拡大に伴う課題への対応、そして未来を見据えた次世代リーダーの育成。これらのチャレンジに対するモノタロウの今後の取り組みは、同社の持続的な成長はもちろん、多くの成長企業にとって示唆に富むものとなるでしょう。その進化から、今後も目が離せません。
MonotaRO(モノタロウ)紹介
モノタロウは、工場やオフィスで使われる工具、消耗品などの間接資材(MRO)を幅広く扱う、国内最大級のオンライン通販企業です。「資材調達ネットワークを変革する」というミッションの下、インターネット技術を駆使して従来の流通における非効率の解消を目指しています。現在単体で、市場シェア3%から2倍以上の拡大を目標に掲げ、16期にわたり毎年二桁の継続的な成長を遂げており、この急成長を支え、さらなる飛躍を実現するために「人材育成」を経営の最重要課題の一つとして注力しています。
