
『NECのカルチャー変革と次世代リーダー育成の取り組み』【セミナーレポート後編】
NECの大躍進に向けての次世代リーダー育成の取り組みについて、個々が強いだけでなく、経営チームとして強くなるために、“エグゼクティブ向けのコーチング”にて、どのような点に注目して進めてきたかを、同社のタレントマネジメントを担当する加藤氏に話していただきました。
INDEX
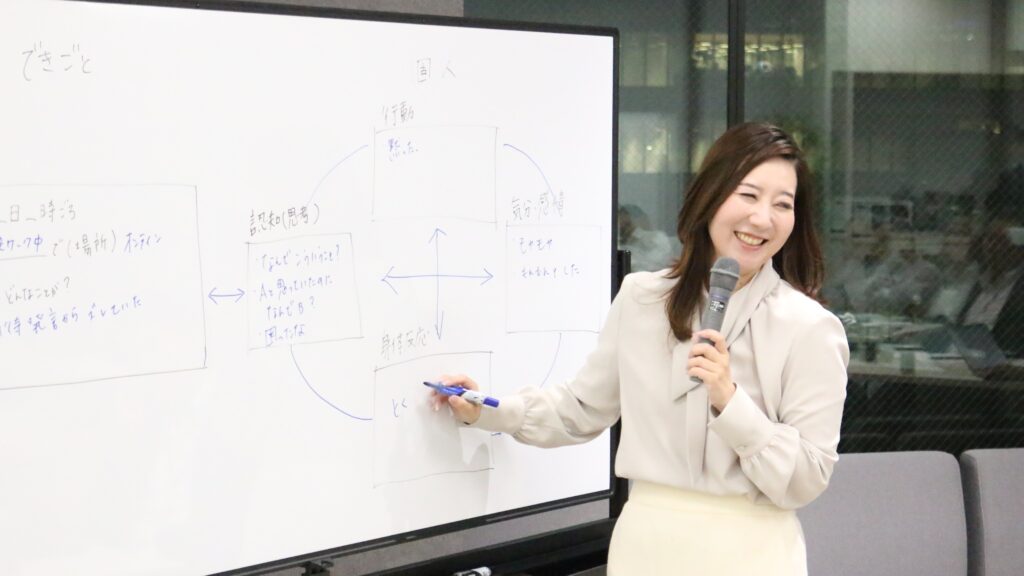

speaker
加藤 久美子氏
日本電気株式会社 ピープル&カルチャー部門 人材組織開発統括部
タレントマネジメント シニアマネジャー 臨床心理士
プライスウォーターハウスクーパースコンサルティング、IBM、ノバルティスファーマにてタレント・アクイジション、タレントマネジメントおよび組織開発に携わった後、大学院修士課程において臨床心理学を専攻、精神科病棟でカウンセリングやデイケア業務を経験。修了後、現在に至るまでNECのコーポレート部門にて、全社のタレントマネジメント戦略およびサクセッションプランニング、育成計画およびその実行をリード。臨床心理士、MBTI Level II、DiSCプラクティショナー。趣味はパーソナルカラーコーディネート、西洋占星術(週末占い師)。
「次世代の強い経営チームを作る」
NECの課題と挑戦
「タレントマネジメントの観点に立った時、ビジネスを伸ばすための経営課題を忘れてしまうことが多くあるのではないでしょうか」
NECのタレントマネジメントを主導する加藤氏は、人材計画においての問題点をこのように指摘しています。
「タレントマネジメントというのは、サクセッションプランが命であって、ビジネスを伸ばすためにおこなうものです。私どものミッションとしては、強い経営リーダーをつくるのみならず、強い経営チームをつくることを目標に取り組んで」いると言います。
リーダー自身のスキルが高く、プレイヤーとして実績を上げてきたベテラン社員は、チームメンバーに自然と高い要求を出してしまう傾向にあります。しかし、現代のリーダーには、「チームメンバーの一人ひとりが自律して社会課題から価値を創造できるよう意見を出し合い、イノベーションを進めていく」、そういうチームづくりをできる能力が求められていると加藤氏は話してくださいました。
成果を出したいがゆえにメンバーへの関わり方に問題がある有能な社員(リーダー)に、そういった意識の改革を起こすことができた一つの方法として加藤氏が挙げてくださったのは、 ”エグゼクティブコーチング” だ。
補足
エグゼクティブコーチングとは
企業のトップおよび経営幹部クラスの方が、より一層優れたリーダーとして周囲に肯定的な影響を及ぼせるようになるための意識変革・行動変革を行っていただくためのプログラムです。
※ビジネスコーチ株式会社サイトより
今リーダーが直面するのは
成功体験を手放す「適応課題」
なぜエグゼクティブコーチングを導入したのかーー。その背景にはさまざまな要素がありますが、加藤氏はその要素の一つとして、現代のリーダーが直面する課題を挙げています。
「リーダーが直面する課題は、技術的課題なのか適応課題なのかという点が重要です。昔は技術的課題だけを解決すればよかったと思います。例えばこの人はファイナンスの知識が足りないということになると、ファイナンスのクラスを取ってもらえばいいわけで、すごくシンプルですよね。
ですが、グローバル化したとても複雑で、不確実な状態の世の中でビジネスをリードしていく、現代のリーダーが直面しているのは、適応課題と言って、自分のこれまでの成功体験であるとか、強く信じてきたものを手放したり、書き換えることが課題になっています。」
とはいえ、自身の成功体験を手放すことが容易ではないことは、想像に難くありません。この「自身の成功体験を手放し、いま求められるものに書き換え適応する」という難易度の高い自己変容を実現させるためには『内省』できること、『自己変容型知性』に到達する必要があると加藤氏は言います。
自身を変える自己変容型知性
到達者はリーダーの中でも ”1%”
成人の知性には三段階(※)あり、(ロバート・キーガン著『なぜ人と組織は変われないのか』)によると、三段階の中で最も高い次元にある自己変容型知性にいたる人の割合は1%程度しかいないといいます。大きな組織をマネジメントしていくリーダーは、大人の知性の段階を開けなくてはならないということで、ほとんどがまだ第二段階である自己主導型知性にとどまっているとのことです。
NECで選抜された幹部たちの特徴として、優秀で、ビジネスに必要なコンピテンシーは満たしてはいても、人材育成力とか組織開発力の領域ではまだ育成の余地があると加藤氏。
「そこでNECではメンタリティーの側面、例えばEQを高めるような部分のように、ヒューマンマネジメント力を強化する機会を会社として提供しています。その一つとしてコーチングの機会を設けています。」
成人の知性の3つの段階
第1段階:環境順応型知性
第2段階:自己主導型知性
第3段階:自己変容型知性
※ロバート・キーガン著『なぜ人と組織は変われないのか』(2013年)
”話すだけ” で改善するのではなく
”行動の変化” で成果を実感し良い循環を生み出す
コーチングについて、トップマネジメント層は自身でも1on1の形で部下におこなっているというNEC。
しかし、選抜したばかりのリーダーのような、はじめてコーチングを受ける人にとっては、 ”話すだけで改善するのか、成果につながるのかと懐疑心を抱く人は少なくないと言います。
とはいえ、それまで「メンバーへの関わり方に難あり」でも成果を出すことに貪欲でリーダーに抜擢された人材は、そのままでいいわけではありません。
NECのエグゼクティブコーチングを担当したコーチによると、はじめは乗り気ではなくても、もともと成果を出したい気持ちや学習意欲の強い人材の場合、変化は起こりやすいと言います。
「コーチングを予定実施回数の半分ぐらいまでおこなった頃、 ”メンバーの関わり方を直すことによって成果が出るのなら、積極的に関わり方を変えていきます” と完全にスイッチが入ったことがわかりました。
その後は、どんどんご本人がコーチングの対話の中で出てきた新しいやり方を試し、行動を変えていくと、成果を実感するようになり、良い循環に変化していきました」
と、その変容ぶりを驚きをもって話しました。
一人ひとりの意識改革と行動変容により
NECの飛躍を後押しする
臨床心理士でもある加藤氏によると、 ”成功するとわかっていても行動を変えるのは7人に1人” というデータもあるとのことで、原因と課題を理解したからと言って行動に移せるわけではないといいます。
しかし、強い経営リーダーや強い経営チームをつくるタレントマネジメントやサクセッションプランニングにおいて、組織のリーダーは中核的であり、組織成長のための重要な存在です。
「この人が良くなることで、このビジネスが伸びる。逆に言うと、この人がこの行動をとっているからこのビジネスが伸びないとか、重要なポジションにつけられない。そういう状況があるのは組織にとって大きな機会損失となります」
という加藤氏にとって、NECが社会価値を提供し業績を安定して伸ばすため、コーチングとともに改革への挑戦は続きます。
