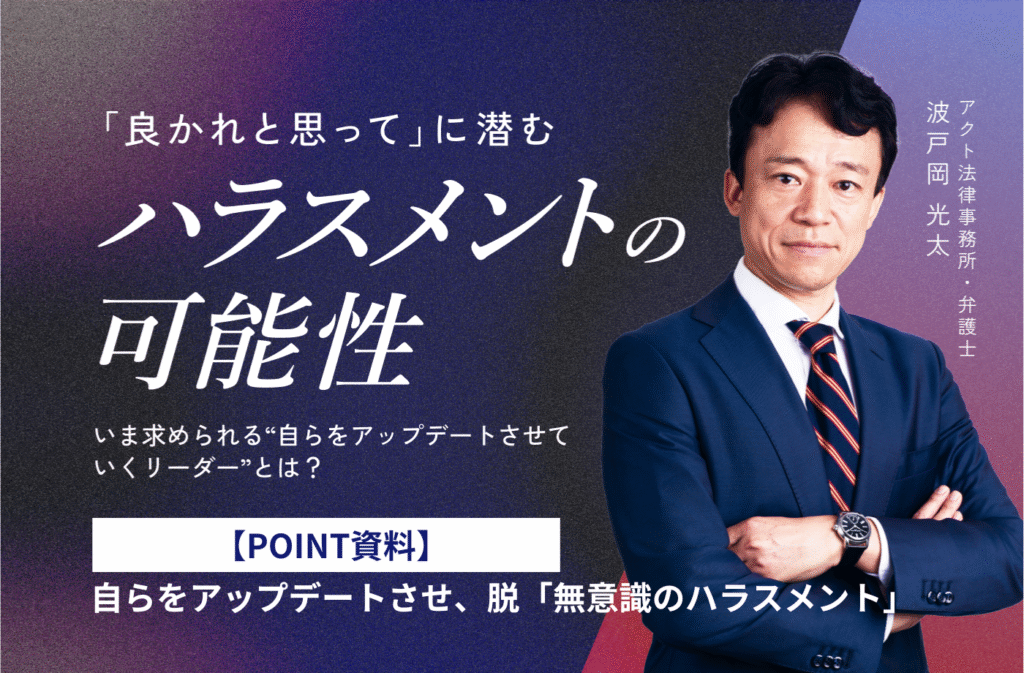「良かれと思って」に潜むハラスメントの可能性【前編】
多くの企業が常に高い関心を寄せている「ハラスメント」の問題は、特にリーダーが意識すべき点であり、企業としても力を入れているところが多いでしょう。しかし本質的な解決に至っていない背景には何があるのでしょうか。
本記事では、「ハラスメントは“誰かの問題”ではなく、“誰もが直面しうる問題”」をテーマに、アクト法律事務所弁護士であり、当社パートナーエグゼクティブコーチでもある波戸岡 光太氏へのインタビューを通じて、その背景からリーダーが意識すべきことを明らかにします。
【本記事のポイント】
〇2020年の「パワハラ防止法」施行以降、企業が本格的にハラスメントの問題に気付き始めた。
しかし、具体的対策方法が分からない企業が増えている。
〇意図せずネガティブな影響を与えてしまうリーダーの特徴として、「本人が気付いていない、
自身の言動がもたらす影響を認識できていない」、また「理解が表面的」が挙げられる。
〇ハラスメントを起こすリーダーには昭和的価値観を持つシニア層だけでなく、
30~40代といった若い層にも多く、誰もが起こす側になる可能性がある。
はじめに
近年、企業におけるハラスメント問題への意識が高まり続けている中で多く耳にするのは、「本人にはその意図がないにもかかわらず、周囲にネガティブな影響を与えてしまっている」という状況です。
「自分はメンバーのためを思って言っている」「良かれと思って指導しているだけだ」――そうした善意に基づく行動が、意図せずメンバーの負荷となり、組織の活力を削いでしまうことがあります。これは決して特定の誰かの問題ではなく、誰もが日々のコミュニケーションの中で、知らず知らずのうちに「意図せざるネガティブな影響」を生み出している可能性を秘めているのです。
今回は、テーマ「ハラスメントは“誰かの問題”ではなく、“誰もが直面しうる問題”」について、弁護士 兼 ビジネスコーチとして活躍する波戸岡氏にお話を伺い、前編と後編の2回わたってお伝えしていきます。

Interviewee
波戸岡 光太
ビジネスコーチ株式会社 パートナーエグゼクティブコーチ
アクト法律事務所・弁護士
認定プロフェッショナルエグゼクティブコーチ
企業とビジネスパーソンをもりたてるパートナーとして、法的アドバイス、対外交渉、契約書作成、人事労務問題の予防・解決を中心に取り組む。ビジネスコーチングスキルを兼ね備える数少ない弁護士であり、依頼者と伴走し解決を目指す取り組みは高い評価を得ている。
クライアント会社は不動産、建築、IT、美容、アパレル、機械製造、教育事業などと幅広い分野に及び、これまでの法律相談数は1000件を超える。
「意図せず」起きるハラスメントの問題
そもそも、ハラスメントに関する相談が増えてきたのは、いつ頃からなのでしょうか?
波戸岡氏
ハラスメントに関するご相談自体は、以前から変わらず存在していたと感じています。私自身、この分野の相談は昔から受けていましたし、当時から対応に困っている企業も少なくありませんでした。ハラスメント問題そのものは、残念ながら世の中で減っているとは言い難い状況ですね。
そうした中で私は、単にハラスメントの法律的な知識や表面的な行動対策だけでは不十分だと感じるようになりました。もっと深いところに、リーダーのコミュニケーション能力や、その在り方そのものに根本的な問題があるのではないか、という問題意識を持ち始めたのです。その問題意識を基に、記事を書いたり、ブログで発信したり、セミナーを開催してみたりしたところ、これまで以上に問い合わせが増えてきたという実感があります。私自身は、日頃、企業の契約書や法的なトラブル、労務管理などについて主に情報発信をしており、ハラスメントはその一部でしかなかったのですが、最近では特にハラスメント関連の問い合わせが増加している状況です。
おそらく、このハラスメントの問題は昔から水面下にあったものの、時代が少しずつ変化してきたのだと思います。もちろん、訴訟になるようなひどいパワーハラスメント(パワハラ)も存在しますが、そこまでいかないケースも非常に多い。そして、そうした「そこまでひどくはないから」という理由で問題に気づかないまま、あるいは見て見ぬふりをする形で企業が運営を続けてしまうと、結果としてメンバーの離職や、理由もなく休暇を取るといったケースが企業において年々増加してきているのです。
そして、様々なニュースや社会的な議論が活発になり、2020年には「パワハラ防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)」が施行され、厚生労働省でもハラスメントが具体的に取り上げられるようになりました。これにより、ハラスメントの問題に企業側が本格的に気づき始めたのだと考えています。ハラスメントの中身自体は昔と大きく変わっていないのかもしれませんが、そこに対して「これはおかしい」「何とかしなければならない」と問題意識を持ったものの、具体的な対策の仕方が分からないという企業が増え、お困りごとが顕在化してきたのが、まさにこの数年です。
波戸岡さんが企業から受けるハラスメントに関する相談において、どのような悩みが多く寄せられますか?
波戸岡氏
私は普段、企業の経営者のサポートをしていますが、そこで頻繁に寄せられるのは、「業務遂行能力は高い、あるいは平均レベルにもかかわらず、コミュニケーション面で課題を抱え、周囲にネガティブな影響を与えている」というリーダーに関する相談です。具体的には、「部下への接し方が厳しい」「不必要な言動が多い」「態度が冷たく感じられる」といった内容が挙げられます。
この点について、リーダー自身が気付いていないケースもあれば、厳しいコミュニケーションをしていることに気付いているケースもあります。しかし後者のケースについては、その事実を周囲から指摘されても、「メンバーの成長を願って指導しているだけなのに、何が問題なの?」「メンバーができないから厳しい指導が必要になっているのであって、それは私の責任ではないよね(部下自身の問題だよね)?」と、自身の言動が周囲に与えている影響を十分に認識できていないのです。むしろ、自身の行動を「良かれと思って」メンバーを育成するための当然の手段である、と捉えていることが多々あります。もちろん、職場での明確なハラスメントや、特定の個人への不当な扱いに関する相談も存在します。しかし、実際には、リーダーのコミュニケーションスタイルが、意図せずメンバーのモチベーションを低下させたり、精神的な負担を与えたりしているものの、本人が気付かない、または自身の責任として認めないという相談が圧倒的です。企業として、あるいは経営者として「どう対処すれば良いのか」と悩む状況が頻繁に生じています。
この“意図せずネガティブな影響を与えてしまうリーダー”には、どのような特徴が見られるのでしょうか?
波戸岡氏
私の経験上、彼らには大きく2つのパターンがあると考えています。
1つ目のパターンは、前述の通り、その事実に気付いていない、もしくはリーダー自身の言動がもたらす影響を十分に認識できておらず、自然と言動に出てしまうパターンです。
私たち自身も、日常会話の中で「なんでできていないの?」や「ふつー、そんなことはしないよね」などといった言葉を発してしまうこともあるでしょう。その言葉1つひとつを振り返れば、あたりの強い、厳しい言い方だと感じますが、かといって「馬鹿」などの直接的かつストレートな批判的ワード(人格否定のようなワード)ではありません。また、特にパワハラにおいては、セクハラやマタハラと違って、「性的なことはしてはいけない」「育児休暇を否定してはいけない」などのように「やってはいけないこと」が判別しづらい。そのためリーダー自身が、何が問題なのかが分からないのです。「相手を無下に否定しているわけではない。「良かれと思って指導している」「正しいことを伝えている(当然のことをしている)」という認識が強く、外部からの指摘を受け入れにくいという特徴が見られます。
2つ目のパターンは、指摘に対して理解は示すものの、表面的な理解にとどまり、結果、指摘された言動を繰り返してしまうパターンです。
周囲から指摘を受けた直後は「そうかもしれないですね」と一時的に反省の色を見せます。しかし、自身の言動がメンバーや組織に与えている本質的な影響や、その根底にある自身の思考・行動パターンに対する深い理解が及んでいないため、結局すぐ元に戻ってしまうのです。
これら2つのパターンより、自覚がないリーダーにどう自覚をしてもらうのかというところで、 悩む企業が多い印象です。
多くの企業が直面し、頭を悩ませているのは、まさにこうした「自身の言動がネガティブな影響を与えていることに自覚できていないリーダーに対して、いかにその自覚・行動変容を促していくか」ということですね。
波戸岡氏
この「自覚」は、ハラスメントの本質的な改善につながるキーワードでもあります。
少し身近な例でお伝えすると、例えば、風邪をひいてしまった時、大きく2つのパターンが考えられます。
1つ目は、「風邪の症状が出ていることに、自身でしっかり気づいている人」のパターンです。喉が痛い、熱っぽい、鼻水が出る、といった症状を感じたら、すぐに「これは風邪だな」と自覚します。すると、病院に行って診察を受けたり、市販の風邪薬を飲んだり、あるいは温かくして早めに休んだりといった、具体的な対策を自ら講じます。その結果、症状は比較的早く緩和し、回復に向かいます。これは、自身で状況を受け止め自覚し、適切な対処法を受け入れることで、好転するというパターンです。
2つ目は、「実は風邪の初期症状が出ているのに、自身ではそのことに全く気づいていない、あるいは認めたくない人」のパターンです。周りの人からは「咳が出ているね」「顔色が悪いよ」と指摘されても、「いや、大丈夫」「少し疲れているだけ」と取り合わない。あるいは、「私に限って風邪なんて引かない」と思い込んでいるために、体調不良を否定してしまうかもしれません。周囲がいくら「薬を飲んだ方がいいよ」「今日は早く帰った方がいいよ」と伝えても、自身が「病人ではない」と思っているため、周囲からのフィードバックを真剣に受け止めません。結果として、薬を飲まない、あるいは飲んだふりをして症状が悪化し、回復が遅れてしまうというパターンです。
リーダーのハラスメントにおける「意図せぬネガティブな影響」も、この「自覚の有無」に起因する側面が非常に大きいのです。
自覚しないことで多くのリーダーは「なんで私がハラスメント扱いされないといけないんだ」、「私が悪いのではなく、できない周りが悪いんでしょ」、「会社は仕事でパフォーマンスを上げる場であり、それができないメンバーを注意した私の何が悪いのか」といった思考になってしまう。だからこそ、「良かれと思って」行うコミュニケーションが、実はメンバーやチームに負担をかけているという状況において、その影響を客観的に認識し、自覚できるかどうかが重要です。そして、その自覚に基づいて、周囲からのフィードバックを素直に受け入れ、リーダー自身のコミュニケーションスタイルをアップデートする行動を起こせるかどうかが、本質的な改善に大きく影響するのです。
誰もが“対象”になりうるハラスメント
「意図せずネガティブな影響を与えてしまうリーダー」は、特定の年齢層やタイプに集中しているのでしょうか?
波戸岡氏
企業からのご相談を受けていて感じるのは、「意図せず負の影響を与えてしまうリーダーは、決して特定の年齢層やタイプに限定されるものではない」ということです。大きく2つのパターンが見受けられます。
1つは、いわゆる「昭和的」な価値観や、80年代の働き方の名残を今も持つシニア層に多いパターン。「自分はこうやって叩かれて、厳しくしごかれて成長してきたんだ。だから、多少厳しく指導したって良いだろう」という、自身の成功体験に基づいた価値観を強く持っています。
昔であれば、「この道20年、30年」という経験豊富なベテランが絶対的なリスペクトの対象であり、その技術や知識は数年やっただけでは到底追いつかない、とされていました。そのような時代であれば、多少「しっかりやれ」といった厳しい言葉も、問題視されることは少なかったかもしれません。
しかし、現在はテクノロジーの進歩が著しく、マーケティング戦略やビジネスの手法も日々変化しています。シニア層の方々の中でも、新しいものに柔軟に対応し、常に自らをアップデートされている方もいれば、過去の延長線上で止まってしまっている方もいらっしゃいます。この「過去の延長線上で止まってしまっている方」の場合、残念ながら、かつてのようなリスペクトの対象として見られにくい状況にあります。つまり、昔は経験を積むほど知見や対応の幅が広がっていったかもしれませんが、世の中の変化に合わせて自身をアップデートしていないと、対応できる範囲が徐々に狭くなっていっているような感覚です。
これはまさに、ストレッチをしていないと、次第に体が硬くなり、可動域が狭まっていく状態に似ています。今年の4月に出した書籍「ハラスメント防止と社内コミュニケーション」でもお話ししていますが、ストレッチは、しなくても生きていけますし、しないからと言ってすぐに怪我をするわけでもありません。現状で動ける範囲はあるから、その中で行動すれば良い、と考えてしまうかもしれません。しかし、何もしないことは「現状維持」ではなく、「後退」を意味します。気づけば昔は届いた手がつかなくなっている、というように。仕事も同様で、同じことだけを漫然と続けている人は、新しい分野への対応能力や、問題解決の引き出しがどんどん狭くなっていきます。
この点に関して、本人はその変化に気づかなかったり、「これで十分だ」と思っていたりします。しかし、新しい仕事に対応しきれていないリーダーを見たメンバーとしては、リスペクトしづらいですよね。そのような状況では、リーダーが自身の限られた世界観のやり方で、可能性に満ちた若手(メンバー)に対して指示をすると、思うようにいかないわけです。「自分の思った通りにメンバーが動いてくれない」「自分の期待する結果が出ない」。それを、往々にしてメンバーのせいにしてしまい、「うるさいな」「なぜできないんだ」といった感情的な反応が出やすくなります。
特にシニア層に多いのが、仕事の幅が狭まりパフォーマンスが低下するだけでなく、感情の許容範囲も狭くなり、怒りっぽくなる傾向です。企業からよく聞くのは、「昔はもっと穏やかだった彼が、最近はすぐに怒るようになった」といった声です。これは感情の可動域が狭まっていることの1つの表れではないかと、多くの方々のお話を聞くたびに感じます。時間が経つにつれて体が硬くなるように、仕事の領域も狭くなっていき、できる範囲も仕事も対応能力も、また感情の対応能力も狭くなってくる。結局思うようにいかないところが怒りや、他人のせいになり、「私は悪くない」、「(まじめに仕事をしてきただけで)間違ったことはしていない」、「こういう時に怒るのは当たり前でしょ」といった思考を生み出すのです。
企業に対してハラスメント研修を行う際には事前にヒアリングをしますが、必ずと言っていいほど「うちの会社ではこういうハラスメントをする人がいる」とか「本人には当然言っていないが、AさんとBさんがハラスメント気質だ」といったアラートを受け取ります。その後研修を行うと、事前にアラートとして挙がっていた方から、「怒るのは当たり前だ」といった反応が出てくる。このように、感情の稼動域が狭くなることによって怒りや、我慢できずにぶつけてしまうリーダーが出てくるのだと感じています。
もう1つは、年齢を問わず多くのリーダーに見られるもので、特に30代、40代といった比較的若い層でも散見されるパターンです。つまり、「シニア世代が引退すればハラスメントがなくなるのか」というと、決してそうではないということです。この若い世代のリーダーの特徴として挙げられるのは、多くの場合、仕事ができ柔軟性にも長けている一方で、コミュニケーション能力の重要性を十分に認識していない、あるいはコミュニケーションそのものに価値を置いていないという点です。
コミュニケーションに価値を置いていなければ、自身の発する言葉が相手にどう受け止められるか、あるいは同じ内容を伝えるにしても、LINEやSNSで伝えるのと、直接会って顔を見て話すのとで、相手が受ける印象がどう変わるか、といった配慮がおろそかになりがちです。効率性や簡潔性を重視する考え方も増えています。仕事の効率化のためにPCやITツールを活用することは重要です。しかし、人間はコンピューターのように進化しているわけではないため、そうしたツールを扱うのと同じ要領で人に向かってコミュニケーションを取ろうとすると、相互理解に齟齬が生じ、人間関係がぎくしゃくしてしまう。つまり、人とのコミュニケーションにおける配慮が、ある意味で不足していると言えるのです。
ちょっとした仕事をお願いする際にも、「やっといて」「できた?」といった端的な言葉だけでなく、「何か自分にできることはあるかな?」と伝えてみる。進捗確認では「できないってどういうこと?」と詰めるのではなく、「今どこまでできているの?」「あとどれくらいかかりそう?」と聞いてみる。このように相手が気持ちよく協力できるようなコミュニケーションの取り方が求められますが、その配慮が不足しておりハラスメント気質になっている方が意外と多いのです。
ハラスメントの問題は個人の資質にのみ帰結するものではないということですね。常に自らをアップデートさせること、またそのうえで、仕事の成果だけでなく、コミュニケーションをうまく取る、人間関係を構築することも会社から求められているリーダーの役割であり、自分の役割なんだと自覚することが重要でしょう。
>>「良かれと思って」に潜むハラスメントの可能性【後編】はこちら
▼要点をまとめた【POINT資料】はこちら