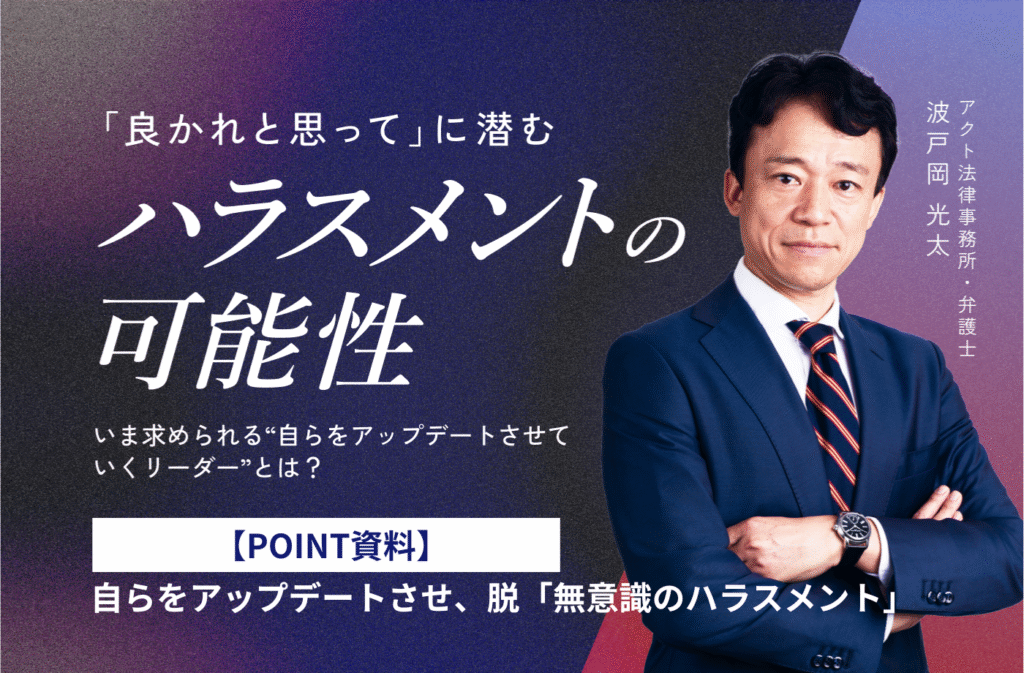「良かれと思って」に潜むハラスメントの可能性【後編】
多くの企業が常に高い関心を寄せている「ハラスメント」の問題は、特にリーダーが意識すべき点であり、企業としても力を入れているところが多いでしょう。しかし本質的な解決に至っていない背景には何があるのでしょうか。
本記事では、「ハラスメントは“誰かの問題”ではなく、“誰もが直面しうる問題”」をテーマに、アクト法律事務所弁護士であり、当社パートナーエグゼクティブコーチでもある波戸岡 光太氏へのインタビューを通じて、その背景からリーダーが意識すべきことを明らかにします。
【本記事のポイント】
〇ハラスメントを防ぐためには継続的なインプットの機会提供と、
リーダーが自らをアップデートさせる意識をもって行動することが大事。
〇「自らをアップデートさせる」うえで、コーチングは非常に有効。
リーダー自身の無意識の偏見や言動の影響に対する気づきを促せる。

Interviewee
波戸岡 光太
ビジネスコーチ株式会社 パートナーエグゼクティブコーチ
アクト法律事務所・弁護士
認定プロフェッショナルエグゼクティブコーチ
企業とビジネスパーソンをもりたてるパートナーとして、法的アドバイス、対外交渉、契約書作成、人事労務問題の予防・解決を中心に取り組む。ビジネスコーチングスキルを兼ね備える数少ない弁護士であり、依頼者と伴走し解決を目指す取り組みは高い評価を得ている。
クライアント会社は不動産、建築、IT、美容、アパレル、機械製造、教育事業などと幅広い分野に及び、これまでの法律相談数は1000件を超える。
リーダーに求められる「人間関係構築力」
リーダーには「仕事の成果」と「人間関係構築力」の双方が求められる中で、実際の現場では成果主義のところも多いでしょう。では、なぜこの「人間関係構築力」が軽視されてしまうのでしょうか?
波戸岡氏
あくまで一般論ですが、日本企業の育成体制として、仕事のスキルや知識を丁寧に教える一方で、人間関係の築き方は個人に委ねてしまっている状況があります。
多くの日本企業では、仕事の成果や目標達成に必要な能力「パフォーマンス力–Performance」についてOJTや研修を通じて育成し、具体的な評価項目が設けられています。一方で人間関係構築力「(集団維持力–Maintenance)」は、「協調性」や「コミュニケーション能力」といった抽象的な評価項目が存在する程度で、明確な育成指導や評価がないのが実情です。そのため、リーダーシップ理論のひとつでもあるPM理論でも表されるように、リーダーの素養として本来は「P(Performance)」と「M(Maintenance)」の双方が備わっている必要があるにもかかわらず、仕事ができるという点だけで評価され、役職が上がる。そして、「人間関係構築力はリーダーである自身の仕事の1つだ」とリーダー自身が自覚していないため、メンバーとのコミュニケーションがうまく取れなくても「自分は悪くない」と考えるようになるのです。
人間関係構築力があまり鍛えられていない状態でメンバーと接し、結果、ハラスメントに繋がるのですね。
波戸岡氏
また、チームの雰囲気もよく、メンバーとの関係性が良好なリーダーがいたとしても、その人の元々の資質だと片付けられてしまい、明確に評価されないため、他のリーダーも人間関係構築力を鍛えようとはならない。結果として、目に見える成果を追求する「P」にばかり意識がいき、人間関係構築といった「M」がおろそかになってしまうのです。
だからこそ、リーダーは、「P」だけでなく意識的に「M」、つまり人間関係を築く力も養わなければいけないですし、企業もそのためのインプットの場を設け、正当に評価をしていくことが重要です。
自らをアップデートさせていくために
これまでのお話を踏まえて、ハラスメントを防ぐために何ができるのでしょうか?
波戸岡氏
ハラスメントを根本から防ぎ、健全な組織を築くためには、企業としての継続的なインプットと、リーダー個々人の「自らをアップデートする」意識が不可欠です。
企業においては、一度きりのハラスメント研修やセミナーで終わらせるのではなく、継続的に学び(インプット)の場を提供していく必要があります。私たちの意識や行動パターンは、一度の働きかけで劇的に変わるものではなく、特に無意識・無自覚の方は治らないしすぐに忘れてしまう。まるで硬くなった体を柔軟にするためのストレッチのように、繰り返し、継続的に取り組むことで、初めて効果が表れるものです。ハラスメントの本質がコミュニケーションや人間関係構築の問題であり、仕事をするうえで常に発生するものである以上、継続的なインプットを通じて、リーダーが自覚し、自身の言動と周囲への影響を深く理解して、より良い人間関係構築のためのコミュニケーションへと意識的に変化させていく土壌を育むことが重要なのです。
そして、リーダー個人に目を向ければ、これからの時代に求められるのは、まさに「オーセンティックリーダー」としての姿です。これは、常に自らの内面と向き合い、学び続け、自己を成長させアップデートしていく、常に人間関係構築としてのコミュニケーション力を高めていくリーダー像を指します。そのために、自身の言動が周囲に与える影響を客観的にとらえる「メタ認知力」を養うことも重要です。今回のハラスメントで言えば、「なぜ今、自分はイラッとしたのだろうか」「あの時、メンバーにもっと良い伝え方はなかっただろうか」と自身を俯瞰して見てみる。そうすることで、自身の思考や感情のパターン、相手との関係性への影響を深く理解できるようになり、自らのアップデートにつながります。
中には、「メンバーを抱えているわけではないから、まだリーダーではない」という方もいるでしょう。しかしそうではなくて、まずは「自分自身のリーダーになっているのか?」、「誰かから言われたからではなく、自分自身進むべき道に向けてリードしているか?」ということが重要なのです。リーダーには大きく3段階(Lead the Self、Lead the People、Lead the Society)あると言われていて、メンバーを率いて、組織を率いるリーダーは2段階目からです。だから、自分自身をリードするということがリーダーのファーストステップであり、メンバーの有無は関係なく、その意識を持つことが大切です。
リーダーの「自らをアップデートする」過程において、有効な手段を教えてください。
波戸岡氏
リーダーが自らをアップデートさせていくうえで、コーチングは非常に有効な手段となります。コーチは、リーダーが自身の行動の根底にある「無意識の偏見(アンコンシャスバイアス)」や「自身の言動が周囲に与える影響」に自ら気づけるよう、客観的な視点と問いかけで「自覚」つまり本人の気づきを促します。この「自分では正しい・当たり前だと思っていたことが、実はそうではない」という気づきは、知識のインプットだけでは表面的な理解にしかなりません。特に自ら発する言葉は、他人に矢印が向いている言葉であるため、自ら自分の言葉を疑うことがなかなかない。「今の自分の言い方は良かったのか」、「指示の仕方は適切だったのか」、「リーダーとして正しいコミュニケーションだったのか」ということを自問自答することがなく気付かないのです。
だから、全体で複数回実施してティーチングする研修だけよりも、コーチが客観的な視点で、実際の状況に近い経験をもとにリーダー自身の内省と気づきを促す方が、効果的であり必要なプロセス。向き合うべきは、個々人の日々の1つひとつの言葉や話し方、働きかけ方の問題であり、そこについて一度立ち止まって考える機会を設けられるため、一人では気づけない部分にもアプローチができるのです。
コーチングにより、リーダー自身のメタ認知を促し、そこで得た気づきがリーダーをアップデートさせるのですね。
波戸岡氏
また、コーチングを導入する際には、外部コーチの活用もお勧めします。ハラスメントが起こりやすい原因の1つに、常に同じメンバーという顔見知りの関係性の中で、時間の経過とともに「身内感覚」になり、コミュニケーションが雑になる、という状況があります。そこに対して外部の視点が入ることで、組織の関係性等にとらわれない、客観的なアプローチが可能になります。外部の人材(コーチ)に対して抵抗感のあるリーダーもいるかもしれませんが、だからこそ、これまで自身の知っていた世界がいかに一部の狭いものだったか、という新鮮な気づきを与えることができるのです。リーダーがより多角的な視点から物事を捉え、コミュニケーションを改善していく大きなきっかけとしての外部コーチの活用は、内部コーチよりも確実に高い効果を発揮するでしょう。
このコーチングに対して抵抗感を感じる方がいた場合は、どのようなアプローチが有効でしょうか?
波戸岡氏
私も含め誰であれ「自分が間違っている」と認めるのは容易ではないですが、アンコーチャブル、つまり他者からの言葉を受け入れることに、より抵抗感を感じる方は、自身の言動が正しいという思いが強い傾向にあります。このようなリーダーに対しては、成功循環モデルで、関係の質から入る必要性や、より良い結果が出る方法としてコミュニケーションの取り方を伝えることが有効です。一方的に「あなたは間違っている」と「ダメ出し」をするのではなく、リーダー自身が求めるゴールやメリットと結びつけて具体的に提示をするのです。
「今のコミュニケーションを変えることで、あなたの仕事のパフォーマンスがさらに向上する」「メンバーとの関係性がより良好になり、ストレスが軽減される」といったポジティブなアプローチが、相手の前向きな気持ちを引き出すことにつながります。
まとめ
ハラスメントの問題は、「良かれと思って」した言動が、知らず知らずのうちにハラスメントにつながっている可能性のある、誰もが直面しうる問題です。特にリーダーは組織を率いていく存在だからこそ、現状に満足せず、意識的に人間関係構築力を高めていく(コミュニケーションの質を高めていく)必要があります。
リーダーである貴方自身がその1人にならないためにも、コーチング等を活用しながら、積極的に自らのアップデートに取り組んでみてはいかがでしょうか?
▼要点をまとめた【POINT資料】はこちら