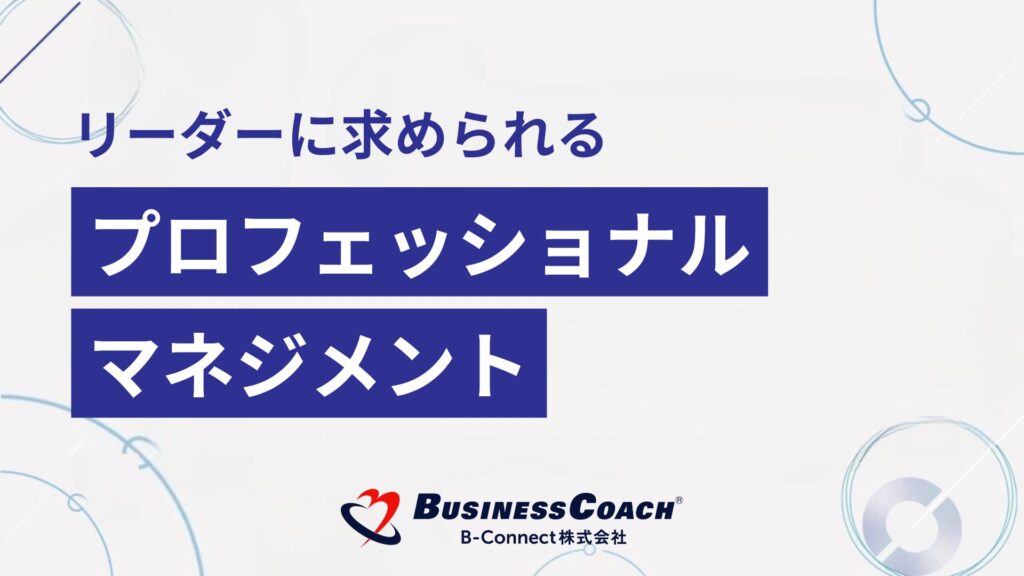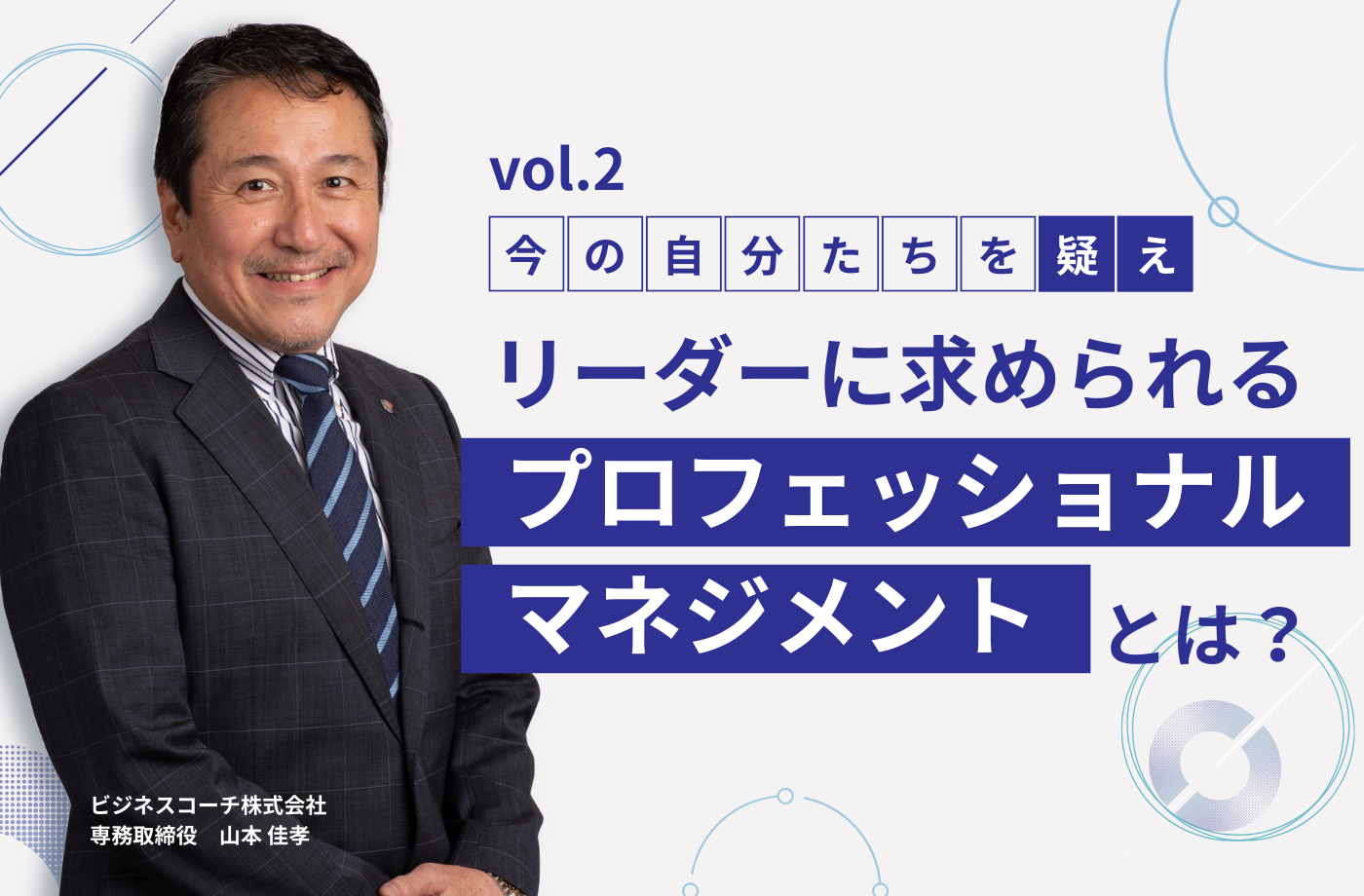
❝今の自分たちを疑え❞ リーダーに求められる「プロフェッショナルマネジメント」とは?【vol.2】
その「当たり前」は、今のあなたにとって最善ですか?
”変化への適応”を苦手とする現代のリーダーは、気付かぬうちに長年の慣習や「ミッションの呪縛」に囚われ、企業の成長を阻害してしまう可能性をはらんでいます。
この課題をどう乗り越え、リーダーのあるべき姿をどのように体現していくのか――。
今回、大手企業を中心にエグゼクティブコーチ 兼 講師として活躍し、あるべき姿を体現していくための1つの手法として動画制作に踏み切った山本 佳孝氏へインタビューを行いました。vol.1~vol.3にかけて、“リーダーのあるべき姿”のカギとなる「プロフェッショナルマネジメント」という概念をもとに、リーダーが固定観念を打ち破り、深く思考するためのヒントを探ります。

Interviewee
山本 佳孝
ビジネスコーチ株式会社 専務取締役
BCS認定 プロフェッショナルエグゼクティブビジネスコーチ
PHP研究所認定 ビジネスコーチ
多摩大学大学院MBA客員教授
ProfileXT®/Checkpoint360™/DiSC®認定ファシリテーター
法政大学法学部卒。PADI Dive Master。広島県出身。大手広告会社に12年勤務後、1995年プルデンシャル生命保険に転職。営業職、営業所長職を経て、2002年、業績最低迷支社の再建を任務に支社長として支社経営に入り僅か1年で完遂し、翌年本社営業推進本部長に就任。2006年にはメキシコ・プルデンシャル設立と営業組織立ち上げを目的に、日本から初代営業本部長として赴任。帰国後は執行役員常務営業本部長に就任。2011年4月、日本グループ内新会社 プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険(株)設立に伴い、初代営業本部長として着任。その後、執行役員専務営業統括本部長として営業体制の構築、更に取締役兼執行役員専務営業戦略本部長を経て人事総務統括、並びにビジネスクオリティ担当役員を歴任。同社の1on1Mtg全社導入の推進役を務める。2019年同社を定年退職し、ビジネスコーチ株式会社に入社し現職。
人材マネジメントの変容と、リーダーの在り方
Q.リーダーが抱える課題に対して、人材マネジメントをどのように変えていく必要があるのでしょうか。
山本氏
人材マネジメントの変容において、旧態依然としたやり方や考え方など前例踏襲を疑い、「これまで正しいものとして教えられてきたことが本当に唯一の正解なのか?」「他にはないのか?」と、積極的に考え行動に起こしていく現場風土を作ることが必要だと考えます。
また、深層的ダイバーシティ(※1)に目を向けることも必要です。
深層的ダイバーシティは従業員幸福度(エンゲージメント)に表れ、生産性やイノベーションに大きく影響します。今、多くの企業がダイバーシティ、つまり前例踏襲を疑い、異なる意見を出しやすくするための“多様性尊重”という点に注目しています。しかし、実際に取り組まれているのは、IR上の分かりやすい表面的な取り組み(=表層的ダイバーシティ ※2)ばかりで、従業員満足度は向上するかもしれませんが、生産性やイノベーションには必ずしも紐づきません。このように表層的な理解で留まっているものに対して、もっと本質を見るように、特に現場のリーダーであるミドルマネジメント層には意識転換してもらいたいです。まさしくこれこそが、人材マネジメントの変容における一番の大きなポイントですね。
(※1)深層的ダイバーシティ
個人の内面に宿る「本質的な違い」に注目した多様性。一人ひとりの価値観や思考、経験の多様性に焦点を当てた状態を指す。
例…性格、価値観、思考様式、宗教、言語、性的指向といった、内面的な特性の多様性や、
働き方、職務経験など
(※2)表層的ダイバーシティ
見た目や制度といった「形式的な違い」に注目した多様性。企業がダイバーシティ(多様性)に取り組んでいると示す際に、外から見て分かりやすい属性に焦点を当てる状態を指す。
例…性別、年齢、国籍、人種、障がいなど、外見で識別しやすい属性の多様性
時短勤務、フレックスタイム制、フリーアドレスといった働き方の制度を導入
Q.本質を見るという点において、なぜミドルマネジメント層に意識転換してもらいたいと考えているのでしょうか?
山本氏
メンバーとの接続面積が最も大きい部長・次長・課長層の方々が意識・行動変容することで、下位層の方々に良い意識・行動が伝染していく――。この流れが、組織全体の変容において最も効率的かつ効果的だと考えたためです。
もちろん、経営層が意識・行動変容し、下位層に浸透させていくやり方が理想です。しかし実は組織のトップである経営層が最も変化しにくい。そのため、経営層から下の階層に向かってオセロのように黒から白に変わるのを待っているのでは、いつまで経っても組織は変わりません。
ミドルマネジメント層の中に、前例踏襲を疑い、積極的に考え、本質に目を向けられる人が何割かずつ現れてくれば、10年後にはきっと組織全体が変わります。中長期的な目線で人材マネジメントの変容および組織の変容に取り組むことが大切です。
Q.人材マネジメントの変容が求められる中で、これからのリーダー(ミドルマネジメント層)はどうあるべきだと思いますか?
山本氏
リーダーの在り方として、自身を取り巻くVUCA要素の強い環境、そして自分自身に起こる(自らが引き起こしてしまう)BANI現象に対して、よりきちんと向き合うことが必要だと考えています。
BANIは割と新しい概念で、Brittle(脆さ)、Anxious(不安)、Nonlinear(非線形)、Incomprehensible(不可解)の頭文字から来ています。VUCAのように、主体が自身を取り巻く環境や社会ではなく、我々「人」を主体とした概念です。
VUCAの次はBANIだというような説明があるようですが、VUCAに対して何か別の現象が起こって、BANIが取って代わるということではないと私は思っています。流行語のように捉えるのは止めたいですね。
VUCAが主に唱えられていた時代においては、世の中の急速な変化や曖昧さをきちんと捉え、それを前提に行動していく必要性が問われていました。しかし、その状況に向き合っている我々も実は非常に脆いのです。
例えば、信念が揺らいでしまったり、以前と主張が変わったりすることもあるでしょう。人はロボットではないため、見た目ほど強固ではありません。我々を取り巻く環境で起こる全ての物事は人が起点となって作られているため、「人は強いものだ」、「盤石だ」と思っていると、実は人を起点として崩れてしまうこともあります。人が作ったものに対して「本当にこれでよいのだろうか?」と不安を持ち始めることもあります。つまり、VUCAという環境の中に、BANIという人を主体とした概念が新たに加わり、これまで以上に複雑さが増しているのが現代です。だからVUCAとBANIのどちらかではなく、両方に対して向き合えるリーダーこそが今の時代に求められていると思います。

>>❝今の自分たちを疑え❞ リーダーに求められる「プロフェッショナルマネジメント」とは?【vol.3】はこちら
▼要点をまとめた【POINT資料】はこちら