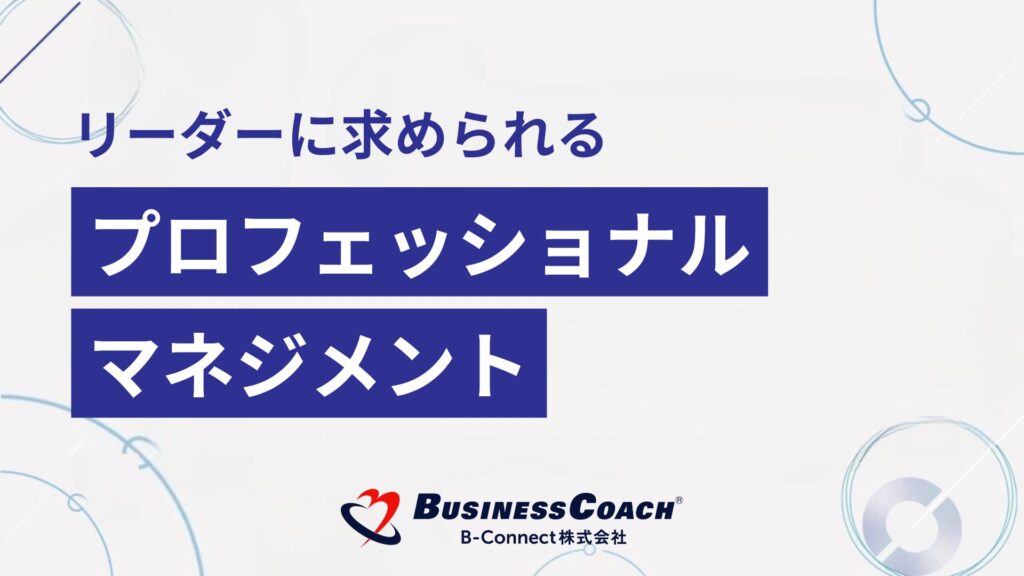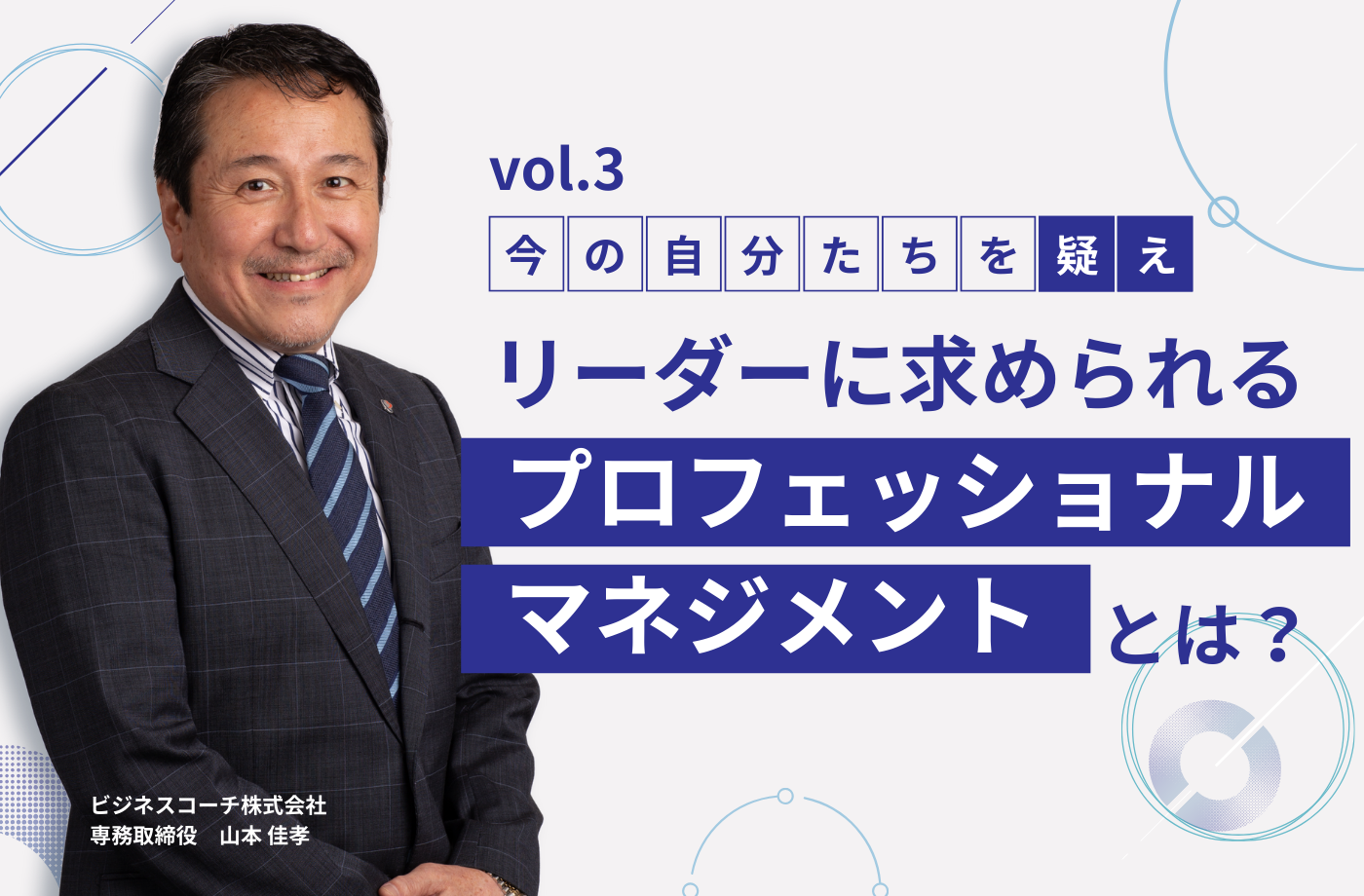
❝今の自分たちを疑え❞ リーダーに求められる「プロフェッショナルマネジメント」とは?【vol.3】
その「当たり前」は、今のあなたにとって最善ですか?
”変化への適応”を苦手とする現代のリーダーは、気付かぬうちに長年の慣習や「ミッションの呪縛」に囚われ、企業の成長を阻害してしまう可能性をはらんでいます。
この課題をどう乗り越え、リーダーのあるべき姿をどのように体現していくのか――。
今回、大手企業を中心にエグゼクティブコーチ 兼 講師として活躍し、あるべき姿を体現していくための1つの手法として動画制作に踏み切った山本 佳孝氏へインタビューを行いました。vol.1~vol.3にかけて、“リーダーのあるべき姿”のカギとなる「プロフェッショナルマネジメント」という概念をもとに、リーダーが固定観念を打ち破り、深く思考するためのヒントを探ります。

Interviewee
山本 佳孝
ビジネスコーチ株式会社 専務取締役
BCS認定 プロフェッショナルエグゼクティブビジネスコーチ
PHP研究所認定 ビジネスコーチ
多摩大学大学院MBA客員教授
ProfileXT®/Checkpoint360™/DiSC®認定ファシリテーター
法政大学法学部卒。PADI Dive Master。広島県出身。大手広告会社に12年勤務後、1995年プルデンシャル生命保険に転職。営業職、営業所長職を経て、2002年、業績最低迷支社の再建を任務に支社長として支社経営に入り僅か1年で完遂し、翌年本社営業推進本部長に就任。2006年にはメキシコ・プルデンシャル設立と営業組織立ち上げを目的に、日本から初代営業本部長として赴任。帰国後は執行役員常務営業本部長に就任。2011年4月、日本グループ内新会社 プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険(株)設立に伴い、初代営業本部長として着任。その後、執行役員専務営業統括本部長として営業体制の構築、更に取締役兼執行役員専務営業戦略本部長を経て人事総務統括、並びにビジネスクオリティ担当役員を歴任。同社の1on1Mtg全社導入の推進役を務める。2019年同社を定年退職し、ビジネスコーチ株式会社に入社し現職。
今に向き合い、本質を捉え、「ヒト」を活かすマネジメントへ――プロフェッショナルマネジメント
Q.今の時代に求められるリーダーのマネジメントスタイルを「プロフェッショナルマネジメント」と定義していますが、これはどういったものなのでしょうか?
山本氏
一言で言えば、「人的資本経営」を現場で実現するための「ヒト」中心の新たなマネジメントのことです。これまでの「コト」、つまり業務やタスクを中心に回していたマネジメントから、社員一人ひとりの「ヒト」の部分に焦点を当てる経営へと、大きく変革していくことを意味し、「プロフェッショナルマネジメント」と名付けました。
現代社会では「人的資本経営」の実現が強く求められています。この人的資本経営とは、社員が最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を築き、一人ひとりの個性や魅力を引き出し、それが企業の成果に繋がるよう支援すること。そして、多様な社員が柔軟な働き方を選び、成長できる環境で幸福感を得て、会社へのエンゲージメントを高めることが、人的資本経営の核心的なマネジメントだと考えられています。
この人的資本経営の実現は非常に難易度の高いものですが、その成功の鍵でもあるのが、現場で社員に最も近い存在のミドルマネジメント層。この層の方々のマネジメント変革こそが、まさにプロフェッショナルマネジメントに求められている役割なのです。
そしてこのプロフェッショナルマネジメントを実践するには、ロバート・カッツモデルで提唱されるヒューマンスキル(対人関係能力)の発揮に加え、高度なコンセプチュアルスキル(概念化能力 ※3)が必要です。このコンセプチュアルスキルは、前述の現代の日本のリーダーが抱える課題やリーダーが変容させていくべき人材マネジメントともリンクしていますが、一朝一夕ではいかないほど習得が難しいものでもあるのです。したがって、後継人材育成計画においては、早期からこのコンセプチャルスキルの醸成に取り組む必要があるということです。
(※3)コンセプチュアルスキル(概念化能力)
物事の本質を捉え、複雑な状況を構造的に理解し、課題解決へと導くためのスキル
今回、この「プロフェッショナルマネジメント」にフォーカスした動画を製作していますが、まさに、“習得が非常に困難だけれども、今を生きるリーダーこそ身に着けるべきマネジメント”をいかにして伝え習得してもらうか?、と考えたことが企画のきっかけですね。
Q.プロフェッショナルマネジメントの実践をテーマとして制作された「プロフェッショナルマネジメント動画」にはどのような制作意図があるのでしょうか。
山本氏
この「プロフェッショナルマネジメント動画」は、当たり前のように見えているものに対して問いを立てる、という構成にしています。一見すると、どこに何の問題があるのかが分からない。何か困っていることもなければ、おかしいとも思わない。こんな状態に対して、「これって本当はどう解釈するのだろうか?」と問いを立て、解釈の仕方を間違えると結果も大きく変わってしまうリスクをはらんでいることを伝えていく必要があると思い、製作しました。
そしてこの背景にあるのは、先ほど申した「日本企業が陥ってしまった経営のジレンマ(ミッションの呪縛)から早めに抜け出す必要がある」という思いです。仕事上で起こる様々な事象に対して、「そのままでいいんですか?」「それは今、舵を切らないと大事(おおごと)になってきませんか?」「自分の思考が固定化されていませんか?」という点に早く気づいてほしい。“コンセプチュアルスキル”と申したように、物事の本質を捉え、とるべき策を行動に移せるようになってほしい。だからこそ、本動画ではテーマを小分けにし、テーマごとに問いを立てるようにしています。
「自分自身の有り様を明確にしなさい」、「自分自身の気づいていないことや弱さを棚卸しして、認識してみてはいかがですか?」といったメッセージも本動画を通して伝えているので、変化への適応力が不足していたり、どこか旧態依然のやり方や考え方に固執してしまっていたりするリーダーにはぜひ見ていただきたいです。
実は過去に成功体験を持っているリーダーほど、自分のその手ごたえのあったやり方から離れることができなかったりしますから、要注意だと思います。
最大の魅力は、自身の「考え」を「具体化」するきっかけを得られること
Q.「プロフェッショナルマネジメント動画」を見ることで、どのような学びや気づきを得てほしいと考えていますか?
山本氏
本動画で得られることは、様々なテーマに対してリーダー自らが「考える」時間を持てることです。本動画をただ見て終わるのでは意味がありません。動画は「あなたはこれに対してどう思いますか?」という問いを立てる形で設計しているため、基本的に答えを出していません。そのため、本動画は自分たちの考えを具体化するためのきっかけであり、考える時間を作るためのツールとして活用いただきたいと思っています。
この動画を活用いただく中で、立てられた問いやメッセージに対して真っ向から否定しても構いません。否定をしたうえで「なぜならば」と自らの考えをもって反論できることが重要なのです。
恐らく日常の業務において、会社や上司から問いが立てられ、そこに対して時間を使って考えるといったことはないでしょう。この動画はその役割を果たすことができると思っています。
“当たり前”を認識し、疑い、考え抜くことこそが重要
Q.「プロフェッショナルマネジメント動画」を視聴するリーダーに対して期待していることはありますか?ゴールのようなものがあれば教えてください。
山本氏
本動画は、「正しい答えを何か1つ見つけに行く」というものではありません。正解が複数あっても、最終的な解に落とし込めなくてもよいのです。前述のとおり、「なぜならば」という理由を用意できれば、問いに対して反論してもよい。つまり、問いに対して考え抜くことが重要であり、本動画でリーダーの方々に期待したいゴールです。
私たちは、物事に対して当たり前と思っているどころか、“当たり前”と認識することもなく前例踏襲を繰り返していることが多いです。そこに対して一度立ち止まって、「これでいいのだろうか?」「やり方は1つだけなのか?」「正解が3つあったらおかしいのだろうか?」といったことを踏まえて、もっと自ら問いを立てて考えていくことが大切です。
しかし、日本人は自ら問いを立てることが非常に苦手。言われた通りに行動する癖がついています。だからこそ、問いを立てて考えるための機会を動画で用意することにしたのです。
特にご覧頂くのがマネジャーやリーダーの方であれば、こうした問いを部下やメンバーたちに投げかけて欲しいですね。部下、メンバーが何を考え、どのような解を導くのかを見て欲しい。こうした対話が自分を育て部下、メンバーも育てることになると思います。
まさにこれが人的資本経営の現場実装の一つだろうと思っています。
「新しさが価値ではない」。今ある知識や考えを「自らの言葉」で語れることが価値
山本氏
また、世の中には多くの動画教材が揃っていて、いつでも見られる環境が整っています。そうした中で、「(気付きを得て行動が変わったわけではないが)人事から言われたので見た」、「動画は見たが何か新しいことを言っているわけでもなかった」で終わってしまい、“新しいことを仕入れられないのであれば価値がない”といった感覚の人が多くいます。
この本質は「知識はあるが、それをどう活かせるのか、どう活かされていくのかを理解しておらず、自分の言葉で語れない人が多い」ということ。本動画を通して考えを巡らせたリーダーの皆さん自身が、また別の問いを自ら立て、その問いに対して自身の言葉で語り、皆で対話をする――。こういった習慣が持てるようになると、これまで何気なく過ごしてきた組織の動き方や在り方に対して疑問を持ち、前例踏襲からの脱却の一歩になるのではと思っています。
ポイント
◆表面的、外形的なものだけでなく、社員一人ひとりの異なる考え方や経験を
組織の力として活かすマネジメントが求められている。
◆「1つの正解」「新しい情報」が常に価値ある重要なことではない。
◆「当たり前」を認識し、疑い、自ら問いを立て、考え抜くことが重要。
◆部下への問いに変え、部下の自律や成長を促す。
リーダーへのメッセージ
Q.最後に、日本企業のミドルマネジメント層(リーダー)に対するメッセージをお願いします。
山本氏
リーダーの皆さんには「これまでや、今現在やっていることを疑いなさい」と伝えたいです。「もっといい方法があるのではないか?」「今やっていることが害になってはいないか?」と、まずは全てを疑い、極端な問いを立てるぐらいのことをリーダーには率先してやっていただきたいと思っています。
前述のとおり、今の日本企業の多くは理念や目標が掲げられるものの、具体的な行動が追いついておらず、外形的かつ表層的な取り組みばかりで、人の違いの本質を活かすという点にあまり着目できていません。10年前、20年前と比較してもほとんどやり方が変わっていない組織が大半であり、本質を見て、本質に対して手を打つことが実は非常に弱いと感じています。
私が実際によくお伝えしている話ですが、例えば多様な人材を採用したいと言葉にしながら、今の自組織と同質的な人材や、自組織のトップが好みそうな人材ばかりを採用しています。しかし本質を見て手を打つならば(本当に多様な人を採用したければ)、「今の会社にいないような人材はいないか?」という目線で選考しなければ組織は変わりません。だからこそ、そういった一つ一つの事象に対して疑問を持つことが必要なのです。
そのうえで、その疑問に対してこれまでとは違う視点から検討したり、突拍子もないような点から考えてみたりしていただきたいと思っています。そして考え抜く中で、今のやり方が最も良い方法だと結論づけられるのであれば、堂々と自信をもって行えばいいのです。
ミドルマネジメント層の方々には、自らの人材マネジメントを変容させ、小さなことにも疑問をもち、本質に即した行動をとれるリーダーになってもらえたらと思います。
⇒プロフェッショナルマネジメント動画はこちら
▼要点をまとめた【POINT資料】はこちら