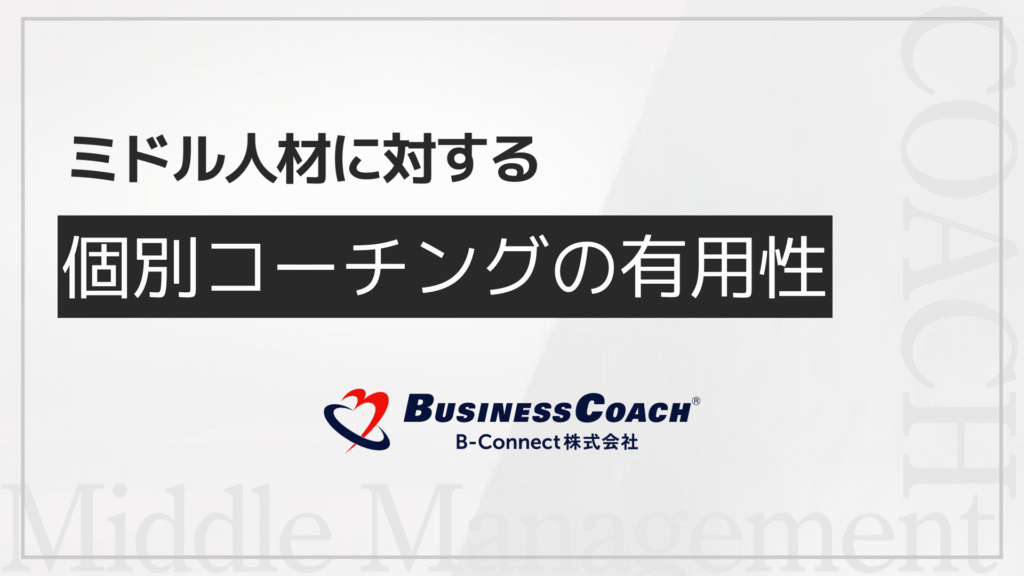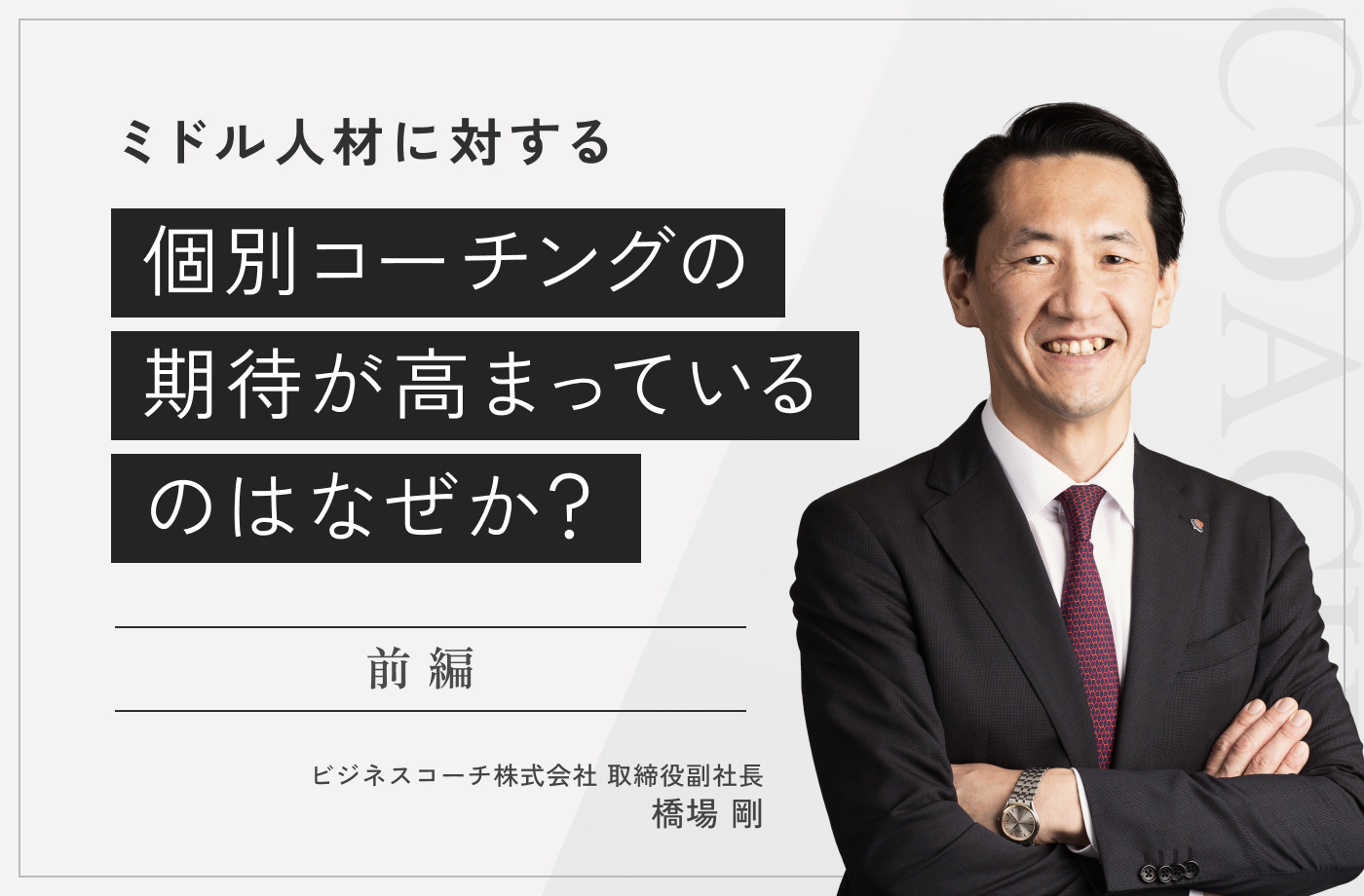
ミドル人材に対する個別コーチングの期待が高まっているのはなぜか?【前編】
今、企業における人材育成のテーマとして、ミドル人材に対する個別コーチングの期待やニーズが高まっています。本記事では、ビジネスコーチ株式会社 取締役副社長であり、エグゼクティブコーチとして活躍する橋場 剛氏へのインタビューを通じ、前編と後編の2回に渡って、その背景から効果、また具体的手法まで明らかにします。
【本記事(前編)のポイント】
〇近年、企業の持続性や継続性が今まで以上に重視されるようになったことを背景に、ミドル人材に
対する育成強化の必要性が高まっている。
〇正解のない現代において成果を出し続けるには、一般的な知識や理論が自社に適合するのか、
行動を起こして知恵や実践知を引き出していくことが大事。
しかし、これまでの集合研修や1対Nの育成手法では限界がある。
〇個別アプローチにおけるキーワードは「ピープルマネジメント」。組織成果の最大化を図る上で必須の
スキルであり、このピープルマネジメント力向上の手法の1つとして個別コーチングが有効。

Interviewee
橋場 剛
ビジネスコーチ株式会社 取締役副社長
BCS認定プロフェッショナルビジネスコーチ
大企業へのコンサルティング業務の経験を活かし、経営者、経営幹部、マネジャー、コンサルタント等、300名以上に対してエグゼクティブ・コーチングを実施し、行動変革・業績向上に寄与する。管理職研修の導入実績多数。
ビジネスコーチ社の経営に携わる一方、企業経営者、管理職に対してワークショップのプロデュース・ファシリテーション等を幅広く実施し、多くの企業経営者・経営幹部・管理職から高い評価を受けている。挑戦し続けるビジネスパーソンを応援し、リーダーと組織に活力を与えるために、人と組織の行動変革とその定着化に力を注いでいる。
なぜミドル人材に注目が集まっているのか?
今、企業における人材育成のテーマとして、ミドル人材に対する個別コーチングの期待やニーズが高まっています。その背景には何があるのでしょうか。
橋場氏
ミドル人材に対する個別コーチングの期待やニーズの高まりには、大きく2つのポイントがあります。
まず1つ目のポイントは「なぜミドル人材なのか?」という点です。
ミドル人材の育成は以前から行われてきましたが、近年では企業の持続性や継続性がより重視されるようになりました。経営幹部が交代すれば経営体制も変わるというのは外資系企業ではよくある話ですが、日本企業の場合、社内でキャリアを積んだ人材がマネジメント層に昇進するケースが多い。そのため、ピラミッドのトップ層だけを育成するのではなく、ミドル層から育成を強化する必要性が高まっているのです。
また、今からミドル層の育成を強化しなければ、将来的な経営人材の不足につながるという危機感も背景にあります。長期的な視点で企業を支える人材を育成するために、ミドル層への投資が不可欠になってきているのです。
次に2つ目のポイントである、「なぜ個別のアプローチが求められているのか」という点ですが、これまでの集合研修や1対Nの育成手法の限界が顕著になってきたことが挙げられます。
多くの企業では、階層別研修など、何かしらの研修プログラムが実施されていると思います。もちろん私たちも研修事業を行っているので、研修そのものが悪いものだとは思いません。しかし、それだけでは実務への活用が十分に進まないという課題が浮き彫りになっているのです。
「研修をやったが、結局は実務に活かせていない」
「研修を受けたときはいい勉強ができた、学びがあった、気づきがあった」
「しかしその後、実際に行動が変わったり、実践で活かしたり、というところまではやりきれてない」
研修だけでは、本当の成果には到達しないのではないか?と気づき始める企業が増えてきています。
つい先日も、集合研修に対する限界を訴えた問い合わせが入ってきたそうです。
橋場氏
「社長候補の優秀人材に対して、様々な研修を行ってきたが変化が見られない。そのため、個別のコーチングを通じた個の課題解決や、外部からのサポートによる学び・刺激を得る機会をつくりたい」
これは先日、当社に入ってきたある企業からの問い合わせです。これは社長候補の人材に関する問い合わせではありますが、これまでに行ってきた集合型アプローチが効果を発揮せず、最後にできることはないか、と個別のアプローチに期待を寄せてくれたものです。
究極的なオーダーメイドの対応ができるアプローチは、おそらく1対1のアプローチ以上にはないでしょう。
「10人いれば10通り、100人いれば100通り」の支援――。
だからこそ、研修に加えて、痒い所に手が届くような個別フォローや個別コーチングを取り入れることが、受講者一人ひとりに最適化された支援となり、本当の意味での成果につなげるための取り組みになると、関心が高まっているようです。
今、個別アプローチが求められる背景
ではなぜ、今のタイミングで個別にアプローチすることが求められているのでしょうか。
橋場氏
この背景には、“環境の変化による学び方の変化”があると考えています。
およそ35年前の1990年頃、日本企業は世界の市場で圧倒的な競争力を誇り、世界時価総額ランキングのトップ10に7社もの日本企業が名を連ねる状況でした。上意下達のやり方が機能し、「多くの企業が確立された成功パターンを持っていたのです。
しかしその30年後の2020年には、トップ10に入っていた日本企業は圏外となり、これまでの成功の方程式が不確実なものとなりました。
正解のないこの世界においては、経営層が絶対的な正解を持っているとは限らず、だからこそ企業は、現場レベルで試行錯誤しながら迅速に対応することが求められるように変化したのです。
つまり成果を生み出すためには、一般的な知識や理論が果たして自社に適合するのか、行動を起こして知恵や実践知を引き出していく、ということが欠かせないのですね。
橋場氏
しかし、多くの企業が行っている集合研修では、知恵や実践知を引き出すことまではできません。だからこそ、コーチングといった個別のアプローチを用いるのです。私たちも20年前からコーチング等の個別のアプローチを行っていますが、20年前と今を比較すると、より今の方が、個別のアプローチに対してフィット感が出てきていると感じています。
また、オンラインの普及による影響もあると考えています。
YouTubeやSNSなど、無料のオンラインコンテンツを通じて、ビジネスにまつわる基本的な用語や知識を手軽に学べる時代になりました。
これにより、わざわざ全国から社員を集めて集合研修を行うよりも、個別の課題に応じたフォローをする方が効果的だと考える企業がここ数年増えているとのことです。
橋場氏
当社で行っている企業に対する1対1の個別支援額も、この2年で約2倍になりました。ここからも個別のアプローチに対するニーズが急拡大していると感じています。
そして個別のアプローチは、費用対効果も高いと考えられています。
例えば100万円の予算を使って集合研修を実施する場合と、1人10万円の予算で10人の個別フォロー(個別アプローチ)をする場合で比較してみます。
まず100万円かけて集合研修のみを行った場合、結局のところ、研修のやりっ放しになるため、学びが活かされず、 現場で実践するところまでは繋がりにくい。
つまり100万円かけたのに100万円の成果どころか、かけたお金の投資額に見合わない形で終わってしまう、といったことになりかねないですよね。
一方で、1人10万円かけて10人の個別フォローをする場合です。私たちも、研修を受けた人が学びを現場で実際に使えるようになるまでフォローすることを目指していますが、 例えば10人のうち半分の人が実行して成果に繋がれば、少なくとも投資に見合うリターンを超えるきっかけになっていると言えるでしょう。
時代の変化により、集合研修から個別に向き合いフォローをしていく必要性が高まる中で、企業の人事にはどのような影響をもたらしているのか、着目してみたいと思います。
急激に忙しくなった人事。人事が抱える悩みとは
一斉実施が可能だった集合研修から個別に向き合いフォローをしていく必要が高まった時代へと変化しました。この時代の変化により、現代を生きる企業の人事は、どのような悩みを抱えているのでしょうか。
橋場氏
企業の人事の方と対話をする中でよく感じることですが、今の人事担当者はとにかく忙しい。確立された成功パターンを持っていた1990年頃に比べ、格段に忙しくなりました。
以前は、確立された評価制度を運用すれば組織は回っていましたが、社会環境の変化により、現在は評価制度の見直し、ジョブ型雇用の導入、1on1ミーティングの普及、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)など、多くの課題に取り組まなければならなくなっています。
さらに、ユニクロ社の柳井氏の書籍タイトル「一勝九敗」という言葉のように、今の時代のビジネスは少なくとも10個の仕掛けのうち1個当たればよいという世界。多くの課題に対して今の時代・今の組織に適した形を見つけるために、試行錯誤をスピーディーに行っていくことも求められています。
その結果、人事は人材育成に十分なリソースを割くことが難しくなっているのです。
だからこそ、私たちのような会社に対する人材育成のアウトソーシングが選択肢の1つに入っています。しかし、評価制度の設計と運用、育成施策の策定と実行は異なる領域であるため、すべてを外部に依頼するというわけにはいかないのが実情です。
急速な時代変化により忙しさが増した今、企業の人事は、人材育成に対して労力を割くことが難しい状況にあるのですね。
橋場氏
特に成長している会社ほど、事業の成長に対して人の成長が追い付かないという問題が浮上しがちであり、人材育成は必要不可欠です。企業が求める人材像は今も昔も変わらず自律型人材であり、手取り足取り教えなくても、自ら考え動き、必要に応じて上位層を巻き込んでいける人材が現場に多い組織は、企業規模に関わらずやはり強い。しかしその育成が間に合っておらず、フォローしなければいけない人材を現場が多く抱えているという点にも、企業の人事は悩みを抱えていると思います。
悩みの種である人材育成ですが、冒頭にあるように、これまでの施策(集合研修や1対Nの育成手法)では成果創出が難しく、別の角度からアプローチしていくことが求められているようです。
個別のアプローチにおけるキーワード
今後人事が検討していくべき個別のアプローチについて詳しく教えてもらえますか。
橋場氏
まず個別アプローチにおいて、企業の方から相談が増えているキーワードは「ピープルマネジメント」です。ピープルマネジメントとは部下を育成する力や、メンバーを動機づける力を発揮することで組織成果の最大化を図るマネジメント手法であり、1対1だからこそできる領域だと考えています。このピープルマネジメント力の向上を目的に、今、大手金融機関や大手生命保険会社より個別アプローチとして個別コーチングのご依頼をいただき、ご支援しています。
組織成果の最大化を図るピープルマネジメントですが、このピープルマネジメント力の発揮がうまくいかないがために、企業の研修投資が無駄になり、学びが実務に活かされないという状況があるようです。
橋場氏
今、集合研修での学びを実務へ反映・活用できる状況になるまで、企業としてフォローしきれていないケースが増えています。 実際に企業に対してご支援させていただく中で感じるのは、“学びを活かせていないと感じている受講者”が非常に多いということ。受講者に対して、研修等で学ぶマネジメント理論・リーダーシップ理論、またフレームワークについての理解や、現場での活用状況を1対1の対話(個別コーチング)の際に伺うと、「どこかで学んだが、あまり活かせた経験はない」「全く活かせていない」といった回答ばかりです。
だからこそ、個別アプローチをフォロー施策として実施し、研修で学んだフレームワークの現場実践を宿題として出すことで、気づきや学びが生まれ、そこで初めて学びが活かされるのです。
個別アプローチの手法として用いられる対話(個別コーチング)は、受講者にとって、研修だけでは分からなかった新鮮な経験と言えるでしょう。
>>ミドル人材に対する個別コーチングの期待が高まっているのはなぜか?【後編】はこちら
▼要点をまとめた【POINT資料】はこちら