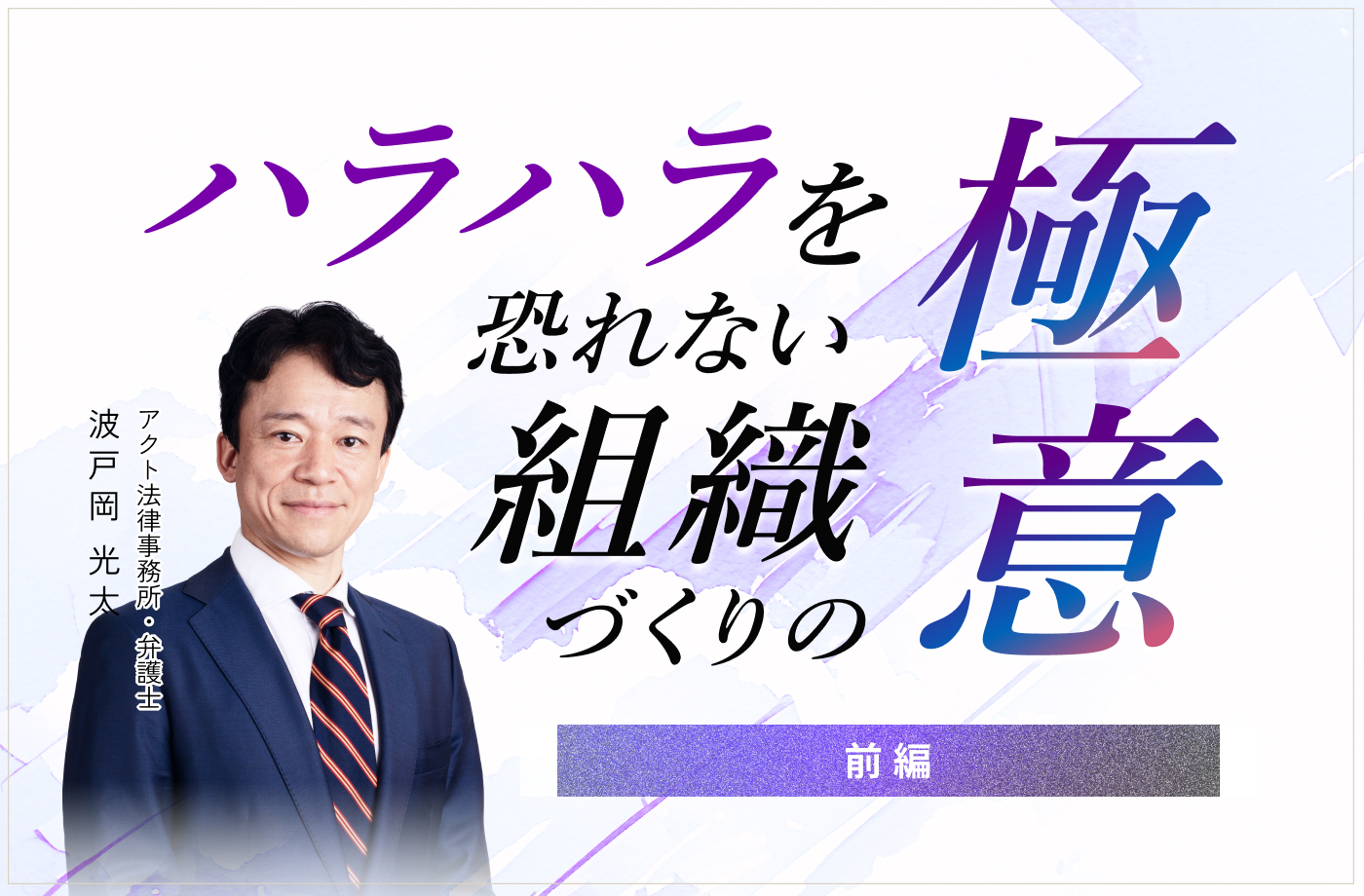
ハラハラを恐れない組織づくりの極意【前編】
ハラスメントの種類が多様化する中で、ハラスメントの「強い立場(上司)から弱い立場(部下)」という構図にも変化が出始めています。健全な関係性からより良い組織成長を図るうえでは何が必要なのでしょうか。
本記事ではこの新たな問題提起である「ハラハラ」について、別記事『「良かれと思って」に潜むハラスメントの可能性』でもお話をお伺いした、弁護士 兼 当社パートナーエグゼクティブコーチの波戸岡 光太氏にインタビューを行いました。ハラハラの実態から、組織に与える影響、また具体的解決策までを明らかにします。
【本記事のポイント】
〇「ハラハラ(ハラスメント・ハラスメント)」は、主にメンバーや下の立場の人からの過剰な反応によって、
上司や経営者が萎縮し、組織のコミュニケーションや指揮命令系統が機能不全に陥る現象。
「自分が組織を動かしている」という認識と心理的反発、また上司や経営者とのコミュニケーション不足
がハラハラを引き起こす背景にある。
〇ハラハラは、上司や経営者の精神的負担の増加(メンタルダメージ)、組織のコミュニケーション不全と
機能低下、そして社員のモチベーション低下と離職の可能性をもたらす。

Interviewee
波戸岡 光太
ビジネスコーチ株式会社 パートナーエグゼクティブコーチ
アクト法律事務所・弁護士
認定プロフェッショナルエグゼクティブコーチ
企業とビジネスパーソンをもりたてるパートナーとして、法的アドバイス、対外交渉、契約書作成、人事労務問題の予防・解決を中心に取り組む。ビジネスコーチングスキルを兼ね備える数少ない弁護士であり、依頼者と伴走し解決を目指す取り組みは高い評価を得ている。
クライアント会社は不動産、建築、IT、美容、アパレル、機械製造、教育事業などと幅広い分野に及び、これまでの法律相談数は1000件を超える。
「ハラハラ」とは何か?
昨今、問題になりつつある「ハラハラ」とは何でしょうか。
波戸岡氏
「ハラハラ」とは、「ハラスメント・ハラスメント」の略称で、主にメンバーや下の立場の人からの「これってハラスメントじゃないですか」という過剰な反応によって、上司や経営者が萎縮し、組織のコミュニケーションや指揮命令系統が機能不全に陥る現象です。このハラハラには主に二つのケースがあると考えています 。
1つ目のケースは、がハラスメントには当たらない、もしくはハラスメントと呼ぶには微妙な事柄に対して、メンバーが「これってハラスメントではないですか?」と過剰に反応してくるケースです。これは一般的にもよく「ハラハラ」の例として挙がりやすいケースですが、このようなメンバーに対して、上司や経営者は結果的に「腫れ物に触るかのようなコミュニケーション」になってしまう。何かを言えばすぐに「それハラスメントですよね」と言われることを恐れて、何も言えなくなってしまうのです。そのため、組織におけるコミュニケーションや指示系統が機能しなくなっており、頭を抱えている企業が多い状況にあります。
2つ目のケースは、実際に過剰な反応をメンバーがしたわけではないにもかかわらず、普段から上司が萎縮ししまっているケースです。上司や経営者の発言に対して、「それってハラスメントですよね」と言われることを恐れ、起こすべきアクションにブレーキがかかってしまう状態であり、これも広い意味ではハラハラの弊害ではないかと思います。
ハラハラと言われるようになったのはいつ頃からですか。
波戸岡氏
ハラハラという言葉が普及したのは比較的最近のことですが、以前よりハラハラのような現象は起こっていたと思います。ある程度、複数の会社や組織で、共通して見られる現象なので、次第にハラハラという名前がつき、言葉が普及していったのだと思いますね。
では、このハラハラを起こす人には、どのような特徴や年齢層の方が多いのでしょうか。
波戸岡氏
実際に企業の方から悩みを聴きますが、別記事『「良かれと思って」に潜むハラスメントの可能性』でお話しした、「意図せずネガティブな影響を与えてしまうリーダー」同様に、ハラハラを引き起こす人に、年齢層やキャリアによる顕著な差はないというのが、私の実感です。ハラスメント気質のある人、つまりハラハラで言えば、上司に当たりが強いメンバーが該当するかと思いますが、非常に年齢の高い人もいれば、入社してまだ間もない若い人もいらっしゃいます。
また、元々ハラハラ気質は見受けられなかったものの、コミュニケーション不全によって、次第にハラハラを引き起こすようになった方もいます。これには、新人で周囲との関係構築ができていないがゆえにコミュニケーション不足が生じている場合と、逆に長く同じメンバーでいるからこそコミュニケーションが減っていく場合とがあります。
会社という閉鎖的な環境下で社歴が長くなり、周囲のメンバーの顔触れも変わらなくなる中で、次第と必要最小限のコミュニケーションしかとらなくなってしまう。すると「元気?」「ありがとう」といった丁寧な言葉ではなく「はい、はい(分かった)」と簡単な言葉や、「それ私の仕事ですか?」などの端的な言葉で終わらせてしまい、実は相手を傷つけてしまっている状況に陥るのです。
別記事で紹介されていたハラスメントの中でも「昔は違った」「昔はもっと素直だった」と言われる方が多いように、元々の気質だけでなく誰もがその可能性を持っているのですね。
ハラハラの実態:企業が直面する課題
ハラハラに関して、実際にどのようなご相談を受けることが多いのでしょうか。
波戸岡氏
基本的には、上司や経営者に対する不満が、いつの間にか攻撃という形に変化することで起きるハラハラのご相談が多いですね。具体的には、上司からの指示や依頼に対して、「これって私の仕事じゃないですよね?」「やらせたくない仕事を押し付けるんですか?」「会社として、私の質問にきちんと答えないのは問題ですよね?」といった言葉が返ってくるといったもの。また、指示や依頼に対応せず、「あの部署は業務改善すべきなのに、全然できていない(業務改善すべきだ)」「あそこに新人が入ってきたが、教育がなっていないのは問題だ(もっと新人教育をしてほしい)」といった、様々な要求を言ってくることに悩んでいる企業が多いです。
そのほかに、自分にとって不都合な話に対して「それ、ハラスメントではないですか?」と不満をぶつけられることで起きるハラハラもありますね。
また、ハラハラのご相談として、「良かれと思って様々なところに口を出す人」のお話も受けます。
例えば、多様性が尊重されつつある時代になった一方で、実際にはその国や企業のやり方に従ってもらう必要があり、それがうまくできていない人がいることで発生するケース。このケースでは、たとえ上司や経営者が理解をしていたとしても、「〇〇さん(上司・経営者)は分かっていないです。自分は多くの経験を積んできたが、このやり方はとてもじゃないけれど、今の時代でやっていけないですよ」と言われてしまうのです。
このように色々なものが目に入り、「私は真面目にやっているし、組織のために不可欠な人間だ。それなのに周りが分かってなさすぎますよね」「こんなんで職場の安全を守れるんですか?」「労働基準法違反じゃないですか?」などとコンサル的に言ってくる人がいる場合、実は法的に問題がなかったとしても、上司や経営者は不安に駆られ、結果、ハラハラが引き起こされています。
こういったハラハラが、上司や経営者のメンタルに影響を及ぼし、相談が増えている状況にあるようです。
波戸岡氏
単に不満を言われるだけではなく、「これはハラスメントです」「法律違反です」などと言われてしまうと、上司や経営者は法律違反に当たるのか不安になり、私のところにご相談が来ます 。しかし、おそらくその手前の段階で、「わざわざ弁護士に相談するほどのことではないけれども、どうしたものかな?」と相談できずに悩んでいる人も多いのではないかと思います。
ハラハラが組織にもたらす影響
相談が増えているハラハラですが、このハラハラによって、組織にどのような影響が出るのでしょうか。
波戸岡氏
ハラハラが組織に与える影響は大きく3つです。1つ目は、上司や経営者の精神的負担の増加(メンタルダメージ)、2つ目は組織のコミュニケーション不全と機能低下、そして3つ目は、社員のモチベーション低下と離職の可能性です。
まず1つ目の「経営者の精神的負担の増加(メンタルダメージ)」ですが、上司や経営者は必要以上に気を遣うようになり、その人との関わりに慎重にならざるを得なくなります。
ハラハラをしてしまう人は仕事のできる人材であり、その人のポジションを別の人に依頼することが難しいケースが多いです。そのため、「もう少し当たりが柔らかくなってくれたらな」と思いながらも、仕事は頼まざるを得ない。だから、その人とは対話をするのではなく、最小限の仕事の指示だけをしてお願いをするといった構図が出来上がるのです。
ハラハラの問題が深刻な場合には、上司や経営者が、自身の発する言葉に対してどのような言葉が返ってくるのかをひどく不安視し、相手に対して一生懸命に気を遣うようになり、結果的に大きくメンタルヘルスを損なうようになります。
2つ目の「組織のコミュニケーション不全と機能低下」は、前述の1つ目の影響によって生じるものです。
ハラハラをする人に対して、上司や経営者が過度に気を遣ったコミュニケーションをとっている姿を他のメンバーは普段から目にするため、当然、自分たちもそのハラハラをする人との関わりを避けたいと感じるようになります。しかし、ハラハラをする人が上司または同じチームに属する場合、どうしても接点が生まれてしまう。特にその人が仕事の実権を握るポジションにいる場合、メンバーは「上司や経営者に助けを求めるのは難しい」ことを察する中で、その人に嫌われないよう最低限のコミュニケーションに留めるようになるのです。
例えば、社内で主要顧客を担当するベテランの営業担当者がハラハラをするケースで考えてみます。この担当者が顧客に関する詳細な情報を握っており、キーパーソンとの強い関係性も保持している中で、上司が新しい営業戦略の提案や他メンバーとの顧客共有について意見をする場面もあるでしょう。そんなとき、この担当者から「今までこのやり方でうまくいっているので、変えるのは無理です」「余計なことをして顧客との関係にヒビが入ったら責任を取ってくれるんですか?」と強く言われてしまい、周囲は何も言えなくなる。そうすると、顧客に関するリアルな状況やニーズなど必要な情報が上司に上がってこなくなり、全体像が把握しづらくなるだけでなく、組織として臨機応変な対応や新しい戦略立てが困難になります。
ベテラン営業担当者が顧客情報と営業活動の重要な部分を「占有」しているかのような状態となるため、組織全体における変化への対応力が著しく低下するということですね。
波戸岡氏
そして3つ目は「社員のモチベーション低下と離職の可能性」です。
上司や管理職だけでなく周囲にいるメンバーも、ハラハラをする人に対して個別の仕事の依頼や相談がしづらくなります。また、「あの人がいる限り、自分の仕事は変わらないだろう」 、「提案や意見はどうせ通らないだろう」と、昨日の延長で続いていく仕事や職場環境に対してモチベーションが低下するだけでなく、離職を検討し始めるメンバーも出てくるようになるのです。
今の時代、転職に対するハードルが低くなったこともあり、「面倒なことに関わるぐらいであれば、転職したほうが良いのではないか」と考える人が増えていることも、この3つ目の“離職”を促していると言えそうですね。
波戸岡氏
ハラハラをする人に年齢層やキャリアによる顕著な差はないとお伝えしましたが、組織に及ぼす影響の大きさで見たとき、特に情報や仕事における権限をある程度持っている人のハラハラはより根が深い問題となります。
もちろん、新人や新任者から言われる文句や不満に対して、ハラハラを恐れるがゆえに仕事が頼めない、精神的負担が増加するといった問題もあります。しかし、情報や権限を実質的に掌握している人にハラハラをされてしまうと、組織自体が機能不全に陥るため、組織に与える影響範囲も大きく、悩んでいる上司や経営者が多いのではないかと、相談を受ける中で感じています。
ハラハラは、一社員の問題だけでは終わらないということですね。
ハラハラが発生する背景
では、そもそもなぜハラハラが起きるのでしょうか。
波戸岡氏
ハラハラが発生する背景には、主に2つの要因があると考えています。1つ目は、「自分が組織を動かしている」という認識と心理的反発によるもの、2つ目は上司や経営者とのコミュニケーション不足によるものです。
まず1つ目ですが、やはり、仕事においてある程度の権限を持てるようになって、自身の力で仕事や組織が回っていると感じたときに、ハラハラを起こすようになるのだと考えています。
例えば、営業担当者を思い浮かべてみてください。初めのころは、先輩についていきながら、1つひとつ仕事を覚えてがむしゃらに頑張っていたけれど、次第と仕事を1人で回せるようになり、気付いたら部内でもトップの成績を収めるようになっていたとします。すると「自分がいるから組織が回っている」といった感覚を持つようになり、「売上を上げている自分に比べて上司や経営層は何をしているんだろう」「自分のおかげで組織が成り立っているのに、上は何もしてくれない」と感じるようになる。このように感じた営業担当者が、しまいには、上司や経営層からの指示や依頼に対して「現場を知らないのに何を言うんですか」とハラハラを引き起こすようになるのです。
当然、経営層と現場の人が見ているものは異なりますし、役割の違いがあります。経営層はより長期的な視点で物事を捉える一方で、現場は今現在の状況に対して短期的な視点になりがちであり、この視点や役割の違いについては、きちんと理解している人が大半でしょう。しかし中には、「自分が組織を動かしている」という認識が強く、さらに、「分かっていない人にとやかく言われたくない」という感情的な反発が出てくる人もいるのです。
そのような人たちが、自分の理屈や感情を正当化し、自分を守る手段として、自身が持っている知識を使いながら、「法律違反」や「ハラスメント」という言葉を使うのだと感じています。
2つ目の「上司や経営者とのコミュニケーション不足」は多くの企業が抱えている状況ですよね。
波戸岡氏
そうですね。上司や経営者のコミュニケーションの取り方によって、ハラハラが引き起こされたというケースは恐らく多くはない。むしろコミュニケーションが取れていないがゆえに、気づいたら埃が積もっていたかのように、ハラハラされるようになっていたという感じではないでしょうか。もちろん仕事の話はしているため、コミュニケーションを全くとっていないというわけではありません。しかし、直接的に関わる仕事の話が中心で、上司や経営者としての視点や、立場の違いによる役割の違い、また会社全体における売り上げ創出に向けた動きや、その中で相手に期待する役割や機能、位置づけについては話せていないところが多いでしょう。
だから、普段のコミュニケーションの中で会社の数字を見せたり、相手への期待や会社の長期的なビジョン、自身の視点を伝えたりする中で、組織マネジメント全体の話をどれだけ意識的に行えているか、という点が大事になると考えています。
>>ハラハラを恐れない組織づくりの極意【後編】はこちら
